 |
風景を創る
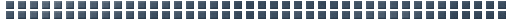
古い街並みの残るガムラスタンの近くに、エストベリ設計のストックホルム市庁舎があります。毎年ノーベル賞の祝賀会が行われるのは、この場所なのです。中庭はレンガの外壁に蔦がからみ、ピロティの柱を通して海が見えます。少し離れて対岸から見ると、建物と海が一体化して風景を創っているように感じました。
ストックホルムには、グンナール・アスプルンドの必見の建物があります。まずストックホルム市立図書館ですが、誰しもが図書館を設計する上でお手本とする建物なのです。玄関から階段を上ると、光の降り注ぐ円筒の大閲覧室があります。個人的な見解ですが、床のデザイン、高窓からの光などはパンテオンの影響なのでしょうか?
森の斎場の写真は、ランドスケープデザインの本の表紙にも使われています。アプローチは長く傾斜しており、歩いていくと、芝生の上に立つ石の十字架が大きくなっていきます。森の小道を歩くと、お墓が芝生の上にきれいに並べられています、まるでモニュメントのように。まさしく、風景を創っているのです。小礼拝堂は木に囲まれており、プロポーションなどが京都の大原三千院に似てるように感じました。内部は屋根形状と違ってドーム天井であり、天窓からの間接光が降り注いでいます。このあたりも、パンテオンの影響なのでしょうか?
(アクセス)
ストックホルム図書館
地下鉄でRadmansgalan下車、すぐです。
森の斎場
地下鉄でSkogskyrkogarden下車、南へ歩いていくと右手に見えてきます。
福祉のまちづくり
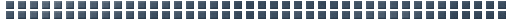
北欧の街では多くの障がい者を見かけます。その街の状況はというと、歩道は石畳で段差が多く、音響信号機や横断歩道部分の段差解消以外は、さほど何もされていません。ただし、バスは低床式で車いすで乗れ、駅にはエレベーターが設置されています。日本と大きく違うのは公共交通のバリアフリー化であり、ちょっとした段差より大きな段差に力を入れているように感じられました。
エレベーターが故障中でベビーカーの人が階段を降りているとき、通りがかりの人が手伝っている姿を偶然にも見かけました。この根底にあるものは何でしょうか?福祉教育の差ではないでしょうか。基本的な「物」のバリアフリー及びそれを補う「心」のバリアフリーが、日本に欠けている点のように思われます。 |