
平成14年4月30日

第 48 号
NPO 岡山県自閉症児を育てる会
![]()
新体制スタートです
新代表からの挨拶
今年度の目指すものについて
第3回 ASC招待ボーリング大会 案内
14年度育てる会総会報告
リーボックの靴を買おう!!
「感覚統合ってなんじゃろか!」若松先生の講演を聴いて
「自閉症児への指導・支援講座」 報告および感想
ボランティア 研修&交流会のお知らせ
夏合宿の計画と参加者募集
山登りのおさそい
第1回 AAO活動のご案内
キッズルームのご案内
勉強会のお知らせ
「OHAの会」
「つくしんぼの会」
「ゆりかご講座」
サッカークラブからのお知らせ
5月度水泳教室のお知らせ
女の子の会のお知らせ
「自閉ワールド」 はみがき・O
私のお薦め本 「レイルマン 〜自閉症文化への道しるべ〜」
近隣の講演会等のご案内
「1歳以前に見られる自閉症の初期徴候について」 平松愛子
事務局だより
掲示板
4コマ漫画 たんぽぽ
![]()
新学期が始まり、皆様それぞれ新しいスタートを駆け出し始めたことと思います。
もう、落ち着かれましたか?
さて、会報でもお知らせ致しましたが、「育てる会」も今年度より新体制がスタート致しました。
長期にわたり代表を務めてこられた鳥羽さんが、総会を以っておりられました。本当にお疲れ様でした。責任を背負うという事は、並大抵の事ではありません。
総会で鳥羽さんは「辛い事はたくさんあったけど、忘れた。楽しい事ばかりが思い出される」といわれました。これは成し遂げた人の味わう充実感なのかもしれません。
来年の今ごろそんな気持ちになれればいいかなと思う次第です。
育てる会は、順々にバトンを渡す必要があります。
なぜなら、子どもが大きくなっていくからです。今までは自分の子どもにとって必要な事を計画してやってきました。それは、子どもが大きくなるにつれて当然形が変わっていきます。
子どもが小さいからということで参加できなかった人が、また参加できない状況になりかねません。
「光る石を落とす企画」として「キッズルーム」が出来ましたが、それもちょっと余裕のできたお母さんに引き継いでいく必要があります。
そして、順々に光る石作戦はつながっていくのが理想的です。(注:「光る石作戦」とは)
仲間を求めて集まった私達は、育てる会で元気をもらい、また元気に子育てをする事ができています。こんないい会は他にはありません。
しかし、順に送るといってもいきなりでは難しいかと思いますので、今年度から少しずつ皆さんにお手伝いいただくことになりました。月当番をランダムに選ばせて頂きました。
皆さんの名前が必ずどこかに入っていると思います。入ってない場合は、ご連絡ください。
1年の中でたったの1ヶ月です。来ていただくのは1回〜2回程度です。
お仕事は「会報発送準備」と「育てる会のお仕事を知っていただく」「太陽の家を知っていただく」などいろいろあります。そこで出会うお母さん達でお茶でも飲みながらお話をしていただく事にも大きな意味があると思っています。よろしくお願い致します。
(都合の悪い方は、個人的に交代ください。変更は必ずご連絡ください)
では、新しいスタートにエイ・エイ・オー!
あれ?ちょっとコーナーが違うなあ。
(K.H)
今年度の目指すものについて
キャッチコピーとか考えるのは大好きです。
「AAO」なんてヒットだと自分でも
にやりと悦に入ってます。
いつもそうありたいと願えば、限りなくそうなっていくと信じています。
そこで、皆さんから寄せられた願いを私的にコピってみました。
みなさんが、同じように唱える事で、育てる会は間違いなくこうなります。
そして、育てる会の目指すものは何と聞かれたら、ババ〜ンとこれを出してください。
もちろん基本は「一人前に育てる」ということです。
そして「親同士、支えあう」ということも忘れないでください。
私達にとって必要なのは仲間です。
仲間で支えあうからこそ元気に子育てできるのだと思いませんか?
「そだてるかいは 花だんになろう
おやは いい土になろう
光と水とようぶんを
子どもは じぶんの 力にしよう
いちにんまえに 咲くために」
つぎに紹介するのは、ノートルダム清心女子大学の平松愛子さんの卒論です。
去年アンケートをに答えられた方は、どのような結果になったかを知りたいと思います。
会報には概要だけを掲載しましたが、全文を読みたい方は、事務局までいらして下さい。
乳幼児のお母さんたちのために、少しでもお役にたちたいとの思いで書かれた論文です。
1歳以前に見られる自閉症の初期徴候について
ノートルダム清心女子大学大学院
人間生活学研究科 人間発達学専攻
008305 平松愛子
はじめに
本研究は1歳以前に自閉症初期徴候は観察され得るのではないかという予想のもとに,すでに診断のついている自閉症児に対して回顧的に質問紙調査を行い,生後1年以内の自閉症児に特徴的に観察された行動特徴を見出そうとしました。
対象
対象はO市および隣接市に住む幼児,児童80名.内訳はすでに診断のついている自閉症児が自閉症児の親の会および療育機関から50名(男:女=37:13),知的障害児が療育機関から15名(男:女=10:5),健常児が市立保育園から15名(男:女=7:8)でした。そのうち自閉症児の親の会に在籍する自閉症児23名以外は全て就学前の幼児でした。
表1
有効回答とされた対象群
対象群 |
人数 |
男/女 |
平均月齢 |
| 自閉症群 | 50 |
37/13 |
79.2 |
| 非自閉症群 | 30 |
17/13 |
62.3 |
知的障害群 |
15 |
10/5 |
57.3 |
健常群 |
15 |
7/8 |
67.3 |
方法
質問紙は本研究の目的に即して,(1)ビデオ解析を用いて自閉症児の早期徴候を観察した6つの先行研究Adrien et al. (1991),Adrien et al. (1993),Osterling & Dawson (1994),Terrelbaum. et. al.(1998),Baranek (1999),Werner, et. al. (2000)において着目された調査項目と,(2)Baron-Cohen et al. (1992)のCHAT(Checklist for Autism in Toddlers),(3)1歳以前頃のわが子についての自閉症児をもつ養育者数名から予備的に得られた回顧的報告等を吟味して27の行動特徴を尋ねる項目で作成されました。
結果
表2
有意差の見られた質問項目に対する回答出現率(%)
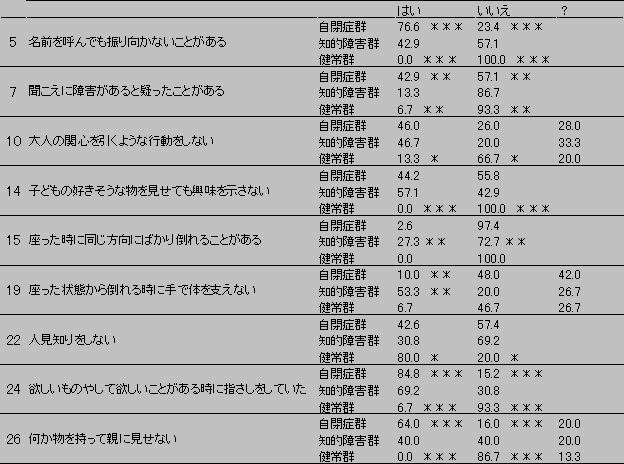
*** p<.001 ** p<.01 * p<.05
表3
有意差傾向の見られた質問項目に対する回答出現率(%)
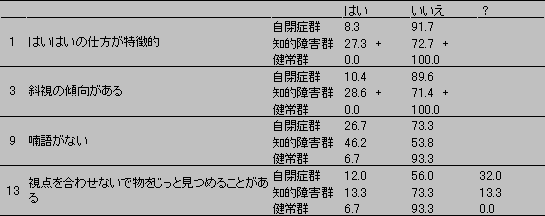
+ p<.10
調査の結果,表2,表3で示した様に,自閉症群では「名前を呼んでも振り向かないことがある」「聞こえに障害があると疑ったことがある」「欲しいものやして欲しいことがあっても指さしをしない」「何か興味のあるものを持って親に見せない」の4つの運動行動特徴に有意差が認められました。これら4つの行動はどれも対人行動や,三項関係が障害されていることを表していました。
知的障害児群では「座った時に同じ方向にばかり倒れることがある」「座った状態から倒れる時に手で体を支えない」という2つの運動行動特徴に有意差が認められました。また,「はいはいの仕方が特徴的」「斜視の傾向がある」の2項目に有意差傾向が見られました。これらの項目は,どちらも対人行動ではなく運動行動の異常を示しています。Terrelbaum. et al.(1998)の示唆したはいはいの異常や座位からの倒れ方の異常などは自閉症児のビデオ解析から見出されたものでしたが,本研究では自閉症群ではなく知的障害群に有意差を持って現れました。これは本研究が知的レベルをそろえることが困難であったこと,被験者からの「 ? 」回答が多く,覚えていない,注意されていた行動特徴ではなかったことなどが影響していると考えられます。
健常群では,「名前を呼ばれたら振り向く」「聞こえに障害があると疑ったことがない」「大人の関心を引くような行動をしていた」「子どもの好きそうな物を見せたら興味を示す」「座った時に同じ方向にばかり倒れることはない」「人見知りをする」「欲しい物やして欲しいことがあるときに指さしをする」「何か興味のあるものを持って親に見せる」という8つの行動特徴において有意差が見られました。これらのうち5つは健常児が1歳以前で必ず行う行動であることは注目されます。
本研究の結果からはホームビデオ解析研究で見られる運動行動の異常は必ずしも自閉症群で見られず,むしろ知的障害群に認められました。またホームビデオで見られる感覚反応異常も自閉症群では必ずしも確かめられませんでした。ホームビデオ解析研究をもとにした回顧的な質問紙調査では1歳以前の乳幼児から自閉症を見出すための運動行動異常,感覚反応異常は見出し得ませんでした。また,「 ? 」回答の多く見られる行動特徴があったことは,回顧的に尋ねているため,被験者である養育者が覚えていなかった行動特徴である可能性があり,養育者がわが子の1歳当時も気付いていなかった行動特徴が存在する可能性も同時に示唆されます。
以上のことから考慮すると,現段階では1歳以前に自閉症の初期徴候を見出すためには生後3か月や6か月に行われる乳幼児健康診断で専門家が診察を行うか,もしくは前方視的なビデオ分析方法を行う必要があると考えられます。筆者の立場からは知能指数をそろえることや前方視的に乳幼児を追跡調査することなどは難しい課題でした。しかしながら,「 ? 」回答が多く見られた行動特徴に,今後は早くから着目することにより,少なくとも今まで気にとめられていなかった1歳以前の乳幼児に対して着眼すべき行動が得られるのではないかと思われます。栗田ら(1991)は『実際の指導上は,自閉的な傾向の有無の把握,言い換えれば広汎性発達障害であるか否かの把握で十分なことが多く,診断確定は慎重になされればよい』と言っています。いたずらに母親の不安をあおることは避けねばなりませんが,本研究で得られたような行動特徴があると知っておけば,まず家庭で療育的なかかわりを始めることができ,自閉症児の持つ障害特徴を抑えることの一助になると思われます。本研究では対象児が調査時に乳幼児期を過ぎているので養育者の記憶にあいまいさがあった可能性や被験者数の少なさなどの問題があります,今後,自閉症児を1歳以前の早期に見出すための留意項目として有用であると考えられます。
本研究は皆様のご協力があったからこそできたものです。今回の調査によって自閉症を乳幼児期に見出す特徴がいくつかあるということがわかりました。
今回の調査結果は自閉症を乳幼児に見出し得る行動特徴が従来から言われている対人行動の特徴に限られていますが、「 ? 」回答の多かった行動特徴はもともと注目されていなかったという可能性も十分に考えられます。
今回有意差の見られなかった14項目のうちいずれかの群で20%以上の回答が「 ? 」に出現している「理由も無いのにすぐ泣く」「物を見る時特有の目の使い方をする」「怖いものがある」「あまり物を怖がらない」などについては,今後注目していくことで新しい結果が得られる可能性も考えられます。また,有意差が見られた行動特徴についても「 ? 」回答を含めた検定が施された3つの質問項目ではほとんど全ての群が20%以上の「 ? 」回答をしていたことは,現在は乳児期にあまり観察されていないがビデオ解析研究から得られた行動特徴が質問紙調査でも有意差があり,今後この項目を重要視して観察すべきであるとも言えそうです。
今回の調査では、自閉症のお子さんの家族,特にお母さん方の多くはお子さんが1歳になる前に何かを察し,不安を感じておられることが明らかになりました。子育てをこれから中心となって行っていくお母さん方への支えとなる相談やカウンセリングを受けられる体制など,養育者の受け皿が必要であることを私は強く感じました。
自閉症の初期徴候に関してHall DMB, Hill P.(1991)は「両親が心配した時に心配しなさい」と述べ,両親からの不安や心配がたとえどんなに漠然として,あいまいであるかに関わらずそれに耳を傾けることを常に重視していますが,本研究でも数名のお母さんから予備的に聞き取った回顧的報告をもとにした項目は「斜視の傾向がある」で有意差が見られました。お母さん方がわが子に対して「なんとなく」「漠然と」感じている自閉症の初期徴候にしっかりと耳を傾け,その漠然とした気付きを何らかの行動特徴として明らかにしていくことは自閉症の初期徴候を見出すことに繋がっていく大切なことだと思います。
調査へのご協力を本当にありがとうございました。
本研究のためにいくつかの文献を調べましたので、もし自閉症の早期発見について、より関心のある方がおられましたら、ご紹介いたしますのでどうぞお気軽にご連絡ください。
以前は「育てる会会報」はHPにも全文をUPしていましたが、容量等の事情により、現在は一部抜粋にさせていただいています。
会の行事の予定は育てる会の「今月の予定」に、近隣の講演会等の案内は「案内板・伝言板」に、また特にみなさんにお伝えしたい記事だけは「育てる会
ライブラリー」に載せるようにしています。
容量は小さくなりましたが、ご覧いただければ幸いです。
なお会報は賛助会員の方へは郵送でお届けしています。
もしご希望の方がおられましたら、ぜひ賛助会員に申し込みをお願いします。年会費
3000円です。
応援よろしくお願いします。)
申込み方法の詳細は「育てる会 HP」に記載しています。