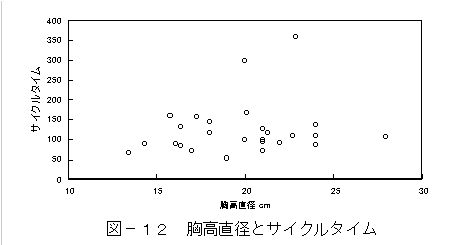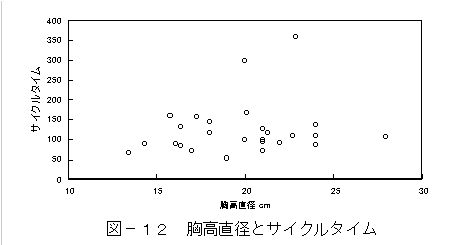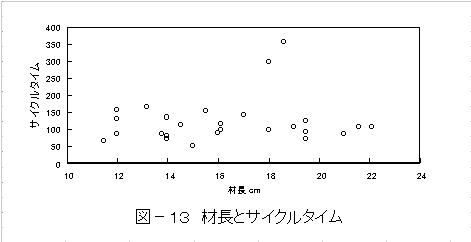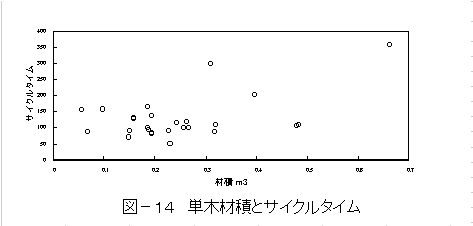7.作業条件と能率
作業能率に影響を及ぼす因子を大まかにまとめてみると以下のとおりである。
・プロセッサ性能
パワーショベルの動力性能、重量、動作速度
扱う材に比べてベースマシンの重量が大きく、強力なエンジンを積んだ機種の方が運転しやすく、能率も高い。7t(0.25m3)クラスの小型の機体のものは間伐材など比較的小径木では能力を発揮できても、胸高直径30cm程度以上の材になると枝払いや材の取り回しに苦労し能率が大きく落ちる例が見られた。
・グラップル能力
材を1本しかつかめない機種と、数本まとめてつかめる機種では作業能率に大きな差がでる。集材が造材に追いつかずプロセッサの待ち時間が大きい作業では全体の能率にあまり顕著な差が現れないが、大量の材を連続して処理する場合は大きな能率の差がでる。特に土場が狭く造材した材を椪積みするか運搬しなければならない時にこの差は顕著である。また、末木枝条処理においてもグラップル能力は作業の能率に大きく影響する。
・材送り速度
パワーショベルをベースマシンとする機体の場合、全体の作業時間に占める割合が小さいこともあって、それほど顕著な材送り速度の違いによる作業能率の差は見られなかった。
・鋸断速度
鋸断時間は全体の作業時間に占める割合が小さく、これによる作業能率の差は見られなかった。ただし、能力ぎりぎりの大径木を鋸断したり、ソーチェンの不良や、ソーモーターの不具合によって、鋸断速度が落ち、材の割れを防ぐため材の端を他の材に乗せるなどの作業が必要な場合は能率は大きく低下する。
・枝払い能力
枝払い能力が低い機種で作業すると、何度も枝払いを繰り返したり、人力による枝払い補助を必要としたりするため作業能率は大きく低下する。機種によって枝払い能力に差があることは観察されたが、具体的に比較検討することはできなかった。また、枝の払い易さは枝の太さだけでなく枝隆の形状などにも影響される。
同一の機種でも油圧回路の調整方法や枝払い刃の形状などによって枝払い能力に大きな差が見られた。岡山県のようにヒノキが中心となる場合はこの枝払い能力が低いものは適さないので注意が必要である。
・作業土場
材の配置、土場の広さ、他の機械との干渉あるいは連携方法によって作業能率に影響がでると考えるが、これについて具体的に検討することはできなかった。
ただし、林道上を土場として利用した場合、同一の現場で集材された材の集積位置によって2倍程度作業能率の差が出た調査例もあり、これらによって相当大きな影響があると思われる。
高性能林業機械の活用すべてにいえるが、現場に機械をあわせるばかりでなく、機械にあった現場を作ることは能率向上や安全の確保に重要である。
・胸高直径、材長あるいは単木材積など材の大きさ
これらの要因がサイクルタイムに影響を与えるのではないかと予想したが、全国の調査結果では図−12、図−13、図−14に示すとおり明確な関係は得られなかった
サイクルタイムの内、枝払い玉切り作業の時間は平均で4割程度であり、またその中でも根株の切り落としや末木の処理にかかる時間は材の大きさにあまり関係がないためと考える。
ただし、サイクルタイムが材の大きさにあまり影響されないということは、能率を材積で表すと、同じ条件で作業しても扱う材の大きさによって大きな差がでるということである。しかし、作業の標準能率を考える場合は作業対象本数だけを考えればよいので作業能率の予測は単純になる。
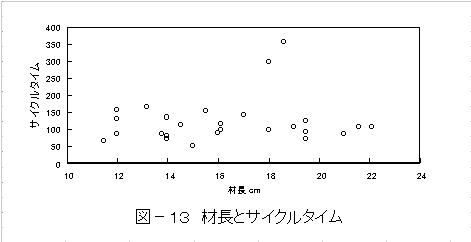
・樹種
ヒノキの大径木や林縁木で枝払いがうまくできず能率が大きく低下する例が見られたが、スギではこのような例は少なかった。
・オペレータの熟練度
現場での聞き取りではオペレータの熟練度が能率を大きく左右すると指摘されたが、それを具体的に調査することができなかった。特に熟練度が経験年数のような客観的な指標のみで比較できない問題点が指摘された。
・測尺精度
導入の初期には寸切れが発生して問題となったが、現在の機種では人力造材に比べて測尺精度が劣ることはなく、必要な測尺精度は確保されていた。ただし、調整ミスや機械の故障があると人力造材と違い大量の不良材が発生するので確実なメンテナンスは欠かせないとされる。
8.生産材の品質
・樹皮むけ、傷

プロセッサの送材あるいは枝払いによって樹皮がむけたり、傷が付いたりする。これについて、プロセッサの導入初期には市場関係者からこれを危惧する声があった。しかし、最近は通常のプロセッサ作業による樹皮むけや傷は製材すれば特に問題になることはないという認識が一般的になってきた。
ただし、丸太といえども商品であり、製材した時に問題ないから外観は関係ないとはいえないので市場の実情にあった対応が必要である。
機種による樹皮むけや傷の付き易さの違いについては検討できなかったが、傷の付き易さと機械的な特性については次のような指摘があった。
・スギに比べてヒノキは枝が堅く、枝払いに失敗した場合に送材タイヤによる傷が付くことがある。
・同一の機種でも送材部の圧接力と送材力のバランスが悪いか油圧油量が不足した場合に枝払いミスが起きやすく傷や樹皮むけが発生しやすい。
9.安全で快適な作業を目指して
ア)プロセッサ導入による労働強度の改善効果
「いったんプロセッサを導入したら、馬鹿らしくてきつい造材作業を人力でやる気になれないですよ。伐木は気分もいいしあまりしんどくないんでいいけれどね」
これが、現場調査で必ずと言っていいほど聞かれる言葉である。林業労働に関する調査によれば伐木造材は4段階に区分した労働強度のもっとも強い労働に当たるとされている。
また、一般的な伐木造材作業の時間で見ると、その作業時間の70〜80%が造材作業で残りの20〜30%が伐木作業である。林試の調査例では1本の伐倒にかかる作業時間のうちチェーンソーの使用時間は平均14%であった。これに対して造材作業はそのほとんど80%以上がチェーンソー作業であった。
このように伐木作業は実際には傾斜地での移動や安全の確認など伐倒そのもの以外にに多くの時間が費やされ比較的楽な作業であるのに対して、造材作業はほとんどがチェーンソーを使いつつ移動する重作業である。この造材作業をプロセッサによって機械化すれば非常に大幅な労働強度の軽減になることがわかる。
イ)労働災害防止の効果
最近5年間の林業における死亡災害の発生状況をみると、全死亡災害件数の内造材作業中のものが12.7%を占めている。このうち集材や輸送はすでに機械化されており機械化によって災害防止をはかる余地は少ない。また、伐木は一部の平坦地におけるハーベスタあるいはフェラバンチャーの導入によって災害防止をはかることが考えられるが、岡山県では一部で導入例があるものの導入の可能性は少ない。
このように、造材を機械化するプロセッサはもっとも実現の可能性が高い災害防止法といえる。
10、おわりに
高性能林業機械の調査研究を始めてから5年がたちました。この間ずっと材価は低迷を続けています。しかし、高性能林業機械の導入と利用は着々と進んできました。物珍しさだけから注目された高性能林業機械も生産性や安全性に熱い視線が集まっています。
岡山県においても西粟倉村森林組合、勝山町の植田産業など着実に実績を上げ手いる事業体があります。このような事業体の先進的な努力に敬意を表するとともに多くを学んで今後の機械化を進めたいと思います。
最後に多くのデータ収集や現地実証試験は数多くの関係者の協力のたまものであったことを感謝します。
執筆担当 中島嘉彦 芦田素広 旦 良則
玉木正夫(現勝英地方振興局) 協力者 藤田 亮(鳥取県林業試験場)