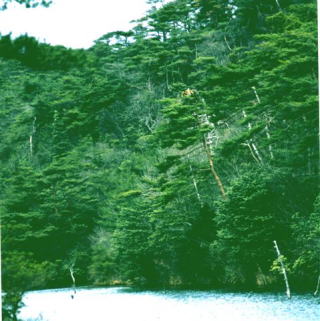|
|
|
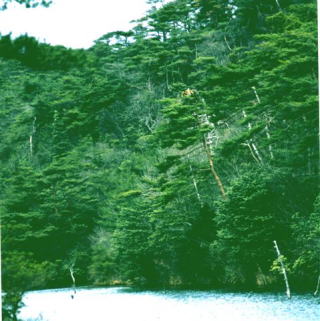 |
|
|
 |
ミサゴ夫婦の一方は枯立木に止まって見張っている。雨が時々ひどく斜めに降る。
ミサゴの背中を強く雨がたたく。濡れてびしょ濡れである。これでは美男美女もだいなしだ。餌を採りにいく気配もない。
観察を始めて四週間近く経過している。あまりにも長い期間抱卵状態が続くのと、連日寒い日が続くので、もうふ化しないのではないかという不安が頭の中を過ぎる。 午前10時にここへ到着して以来、静かな同じ光景が午後3時現在続いており、変化がない。
テントの覗き穴の一つから周囲を見渡すと、新緑を迎える前の暗い山の斜面にタムシバの花が白く点在して神秘的でさえある。雨の中にミサゴはじっと動かない。
晴
時々雨 気温6〜7℃
 |
|
|
山が少し暖かくなった。
4月22日
どうやら待ちに待った雛がふ化したようだ。巣の外縁部にこれまで見られなかった白い固形物が見られる。卵の殻らしい。
観察を始めてから31日が経過した。長くて静かな抱卵期間が終わったようである。
よく見ると親鳥の様子がこれまでと違う。雄鳥が巣の中へ入って巣を守っている。それに雌鳥が何時も座っていた位置に比べて姿勢が高い。そしてす巣の外縁寄りである。時々下を向いては何かを見つめている。赤ん坊に話しかけている母親のような仕草に見える。
雌鳥の様子もこれまでと違う。枯れ立木の枝に止まって雄鳥の監視役と交代してしまった。木の枝の上で動く頻度が高い。それに巣の方向を見ることも多く、そわそわしているように見える。やはり雛の誕生であろう。
そのうち、雌鳥が巣の中へ入った。夫婦揃って巣の中へ入ることなどこれまでになかったことである。
午後になると雌鳥が池の周りを大きく円を描きながら餌を捕りに飛び立っていった。どうやら、餌を捕る役も交代したらしい。1時間20分かけて雌鳥は大きな鯉を捕ってきた。
晴 気温12〜16℃ レンズ 1000mm 増感現像
4月29日
午後、カラスの鳴き声が始まり、それが次第に近づいたかと思うと、数羽のカラスが枯れ立木へ止まっている母鳥を攻撃し始めた。 ミサゴは、ワシタカ科の鳥で恐い顔をしている割には性質がおとなしい。特に雌鳥がそのようで、カラスもこのことをよく知っているらしい。ミサゴの雌鳥は止まる枯れ立木の枝を変えながらカラスの攻撃を交わしていた。カラスは狙いはどうやら巣の中の雛にあるようであったが、巣の方はミサゴの雄鳥が堅く守っているので手の出しようがない。
その内に、カラスのほうも一羽去り、また、一羽去りで、ついに残る一羽だけが執ように雌鳥を攻撃していた。攻撃といっても血を流すような激しいものではなく、からかいのようなものであった。
|

カラスが最後の一羽になったところで、巣の安全が保てると判断したのかついに雄鳥が怒って、雌鳥を助けにものすごい速さで枯れ立木まで行き、カラスを攻撃して撃退してしまった。この一件から推測して、雛がふ化した後に雄鳥が交代して巣を守り始めた理由が分かってきた。どうやら、雛が小さい間は、力の強い父鳥が主に巣の雛を護るようである。
素晴らしい子育ての連携プレー・に関心。言葉を持たない彼らがどうしてそんなことを考えたり、実行できるのか不思議であった。
晴 気温14〜18℃ レンズ 210mm
5月5日
始めてミサゴの雛が巣から頭を出した。小さくて姿勢が低いためか、あるいは頭の重みをささえきれないのか、巣の緑の木の枝の隙間からたまに頚がのぞくだけだ。複数羽らしいが同時に頭が見えないので数は分からない。写真の父鳥の顔の下に頭が少し見える。
雛が少しでものぞくとシャッターを切る、その繰り返しをしばらくしていたが、そのうちついに雛をカメラで捉えることができた。頚は色も形もちょうどウズラに似ている。しかし、くちばしと目はやたらと大きい。蛇鳥のようにも見える。
時々父鳥が身体を移動させるのは、おそらく雛の行動が自由になるようにしてやっているのだろう。
|
|
|
母鳥は昼過ぎに餌取りに出発した。 二時間三十分後に母鳥が帰ってきた。大きな魚を持っている。鯉であった。巣を守っている父鳥が高い姿勢で少しずつ魚をちぎっては巣の中の底にいる雛に与えているようだがはっきりとは分からない。
暖かくなり巣の辺りがすっかり新緑に変わってしまった。
晴 気温14〜18℃ レンズ 1000mm
5月14日
ミサゴの雛が二羽であることを確認した。
周囲の緑が濃くなり、初夏の気配が感じられるようになった。ふ化後三週間以上経過し前回訪れた日から一過間が経ったので雛も大きくなり、頚から上が巣の上へ出るまでになった。その結果、同時に二羽の雛を見ることができるようになった。
雛が少し大きくなり、もうカラスなどの襲撃のおそれが無くなったのか、再び巣に母鳥が入って守り始めた。
父鳥は午前中に一時間二十分かかって魚を取ってきた。雄鳥は巣へ魚を持ってかえると
一緒に魚を食べることもなく、そして、枯れ立木へ戻ることもなく、すぐに出かけてしまった。忙しくなったようである。 |

母鳥が二羽の雛へ交互にくちばしで魚をちぎっては与える。それは約二十分間続いた。
雛はたまに片方の巽を広げて伸ばすが羽根がほとんど生えていない。
曇時々雨 気温14〜18℃
|
|
|
5月14日
食後には巣の外へお尻を向けて、乳白色の糞を飛ばす。
頭部が薄茶色で茶色の縞模様があり、それに不似合いなほどおおきな目がついている。
体は腹胸など全体が薄茶色、そして巽も薄茶に茶色の縞模様がある。いのししの子供と同じ縞模様をもっている。
尾羽根がまだ短いので滑稽な感じさえ与える。 親鳥の五分の一程度の大きさである。
5月21日
雛は身体が母鳥の半分程度に成長した。テントへ入ると間もなく父鳥が帰ってきた。魚を取ってきた様子がみられない。巣の中へ入った父鳥はその中へ残っている餌を盛んに食べ始めた。二羽の雛鳥と母鳥は、父鳥がさかんに食べているのに無関心の様子がみられる.どうやら、食後あまり時間が経っていないようだ。満腹なのだろう。雛達の食べ残した餌を食べる父鳥が哀れな感じだったが、親子一家揃っての写真が1000mm望遠に2倍のテレコンバータを付けることによって撮影できた。雛の頭が白くなり始めた。
時のち時々曇り 気温18〜21℃
5月21日
母鳥は伴侶が長い時間巣に帰らない間に、自分の身の丈の三倍は有るとみられる松の枯
れ枝や水苔を足でしっかりと掴んで持って帰っては、巣の補修をしていた。
6月4日
朝九時にミサゴの撮影用テントへ着いた。ミサゴの雛は無事であった。そして、ずいぶ
ん大きくなっていた。胸と頭が白く、体長ももう親鳥の6割はあるだろうか。
父鳥は何処まで餌取りに行くのだろうか、11時45分に出発した。
時のち義 気温20〜21℃ レンズ1000mm 増感現像
|

6月4日
15時14分に父鳥が餌の魚を鷲づかみにして帰ってきた。餌の魚を捕るのが難しかったのか、カメラを構えて四時間三十分もの長い間、父鳥が帰らなかった。ファインダーによる長時間の連続観察は疲れるが、このようなシャッターチャンスがあるので楽しみである。父鳥がなんとか大きな魚を鷲掴みにして巣に帰ったときには、巣で待つミサゴ達と同様に、約五時間もの長い間ファインダーを覗いていたことからくる疲れを忘れるのであった。 レンズ 1000mm 増感現像
|
|
|
6月10日
ミサゴの雛は親鳥に近い大きさになった。この頃の成長は著しい。
もう親鳥が一緒に巣の中へ入っていられなくなって、近くの枯れ立ち木に止まって見守るようになった。
雛鳥達はときどき巽を広げて羽ばたくまねをする。しかし、一羽が巽を広げると、もう一羽の雛は身体を屈めていなければならない。そんなにまで成長した。
晴 気温22〜25℃ レンズ600mm
6月17日
風は強いがずいぶん暖かくなり、セミの声も聞かれるようになった。
ミサゴの雛達は前にも増してさかんに羽ばたきの練習をしている。巣の下の山肌を木の葉返しに走る風が吹き始めると風上へ向き、巽をいっぱいに広げて風を身体に蓄えている.空を飛ぶ時に備えて力いっぱい練習が続く立派に成長した。
上空をカラスやトビが飛んでも、くるくると首を回したり傾けて、相手を確認するが、雛達は特に驚いた様子もない。
父鳥の餌を持って帰る頻度も高くなった。
|
 |
|
|
6月17日
この頃午後になるといっものように山に強い風が吹く。
その凰はゴーつと鳴りながら池を渡り、一気に山の斜面を這い上がって隣の谷へと移動していく。
風の通っていく方向には次々と木の葉返しの通が数十メートルの幅でくっきりとついては消えて行く。ミサゴの雛は強い風が来る度に、風上に向かって羽根を広げて飛び上がってみる。この日1m位のジャンプがあった。もうすぐ、巣立ちだ。巣立ちの日も近い。
6月25日
梅雨の重り空が続く毎日となったが、今日は幸いにも雨が降らなかった。
十一時にいつものテントへ着いた。 もう、ミサゴの雛達は巣立ってしまっているのではないかと心配しながら山道を急いで来た。
二羽の雛のうちの、一羽はすでに巣立ちを終えて巣から去っていた。しかし、近くでときおり、ピーと声がしているので槍が池のどこかに居るらしい。
巣の中ではもう蔦よりも大きな一羽の雛がじっと親の帰りを待っていた。
カメラのセットにとりかかった。ずっしりと重い望遠レンズが威力を発揮する日が今日であることを感じていた。
長い間、この日のくるのを望んでいた。
雛は風が強く吹き姶めると、その風上へ身体を向けて、巽を広げると大きくジャンプを繰り返している。三メートルは飛び上がっているだろうか。
手間取っているカメラのセットにあせりを少し感じてはいたが、ミサゴの雛がジャンプに続く空中への巣立ちを一気にしてしまうだけの勇気がないことに気づいていた。 カメラのセットを終えると間なしの午後一時頃、母鳥が大きな鯉を片足に掴んで巣へ帰ってきた。
それを見て、既に巣立ちを終えたもう一羽の雛も巣の中へ帰ってきた。巣の中には以前のように三羽のミサゴが揃った。
その後、十分程経た後、父鳥も魚を持って帰ってきた。しかし、巣の中が満員なのを見ると、少し離れた松の木へ止まり、しばらく巣の中の様子を窺っていたが、そのうち自分の持って帰った魚を食べ始めた。
見つめるファインダーの中に、どれが親子か見分けがつかない程に大きく成長した二羽の雛と母鳥の食事風景が展開された。
曇り 気温23〜25℃ レンズ1000mm |
 |
|
|
母鳥は、この巣立ちを終えていない雛に巣立ちを促すかのように雛の方へ向いている。
雛の方を向いて、見つめ、そして、ときどき頭を上下したかと思うと、次には身体を動かして、巣立ちを促しているようであった。
触は向かい風が吹くと、巽を広げて巣から三メートルほど飛び上がるが、なかなか巣から飛び去ってしまうだけの決心がつかない。
「飛べ、思い切って飛ぶんだ!
へっぴり腰じゃだめだ。お前の父母のように空をかけめぐれ。
勇気を出せ。」
レンズ600mm
6月25日
そのうちに、巣立ちのクライマックスが、突然にやってきた。
ファインダーを覗いて撮影のチャンスを待ち始めてから約三時間が経ようとした頃、強い風が池を渡り始めた。
その風はミサゴの巣の有る松の下を走って木の葉の裏を白く見せながら勢いを増していった。
その勢いが松のてっペんの巣へ影響を与えるようになったとき、残る一羽の雛は、母鳥に促されるように巣の縁に立った。
水平方向の一点を見つめていたかと思うと、次の瞬間に若い大きな巽を広げて、巣を飛び立っていった。
そして、勢いよく羽ばたきながら、写真のように母鳥の止まる立ち木の上を通って、垂直方向に大きな円を描いて、元の巣をめざして帰ってきた。半径100メートルほどの大きな円だ。
ところが、この幼鳥は巣の縁まで戻ってきて止まろうとしたが、初めて空を飛んだので速度を落とす加減が分からなかったようである。巣を通過してしまった。そして、再び母鳥の頭上を通って、山の斜面の枯れ木の枝まで行ってやっと止まることができた。ついに念願の巣立ちの瞬間の写真を撮ることができた。
レンズ 1000mm
 |
 |