ナチズム、共産主義、軍国主義、帝国主義、排外主義など深刻な負の遺産を総括する作業から生まれた政治哲学の理論書のいくつかを厳選して紹介する。カルト宗教や、マルクス主義のように、自己満足的な完結理論(閉じた理論、威勢だけ良いプロパガンダ的筆致)ではないので、理解するためには多少の努力が必要。民主主義の本来の意味の通り、定常的な体制論や予言論ではない。この政治哲学者たちの新しい試みと提言を、活かすも殺すも、老年世代の反省と、壮年世代の内省、そしてなによりも若い世代の活躍にかかっている。
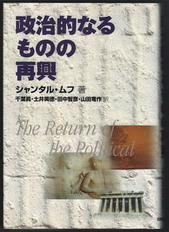 ベルギー生まれの女性政治哲学者シャンタル・ムフはこの著書で民主主義を「闘技」と呼んだ。民主主義と自由の相克、道徳や善、正義の関係を考察・提言している。この政治哲学を理解しておけば、軽薄なコメンテーターの評論に惑わされることもなく、市民が行うべき役割を息長く続けることができる。政治は、傍観の中には一切ないからだ。「混迷・迷走を深める社会」を目の当たりにしても、民主主義の不確実性を受け入れ、備えを怠らず、市民が政治家以上の闘技のスキルを磨く良いチャンスの到来とみることができるからだ。 ベルギー生まれの女性政治哲学者シャンタル・ムフはこの著書で民主主義を「闘技」と呼んだ。民主主義と自由の相克、道徳や善、正義の関係を考察・提言している。この政治哲学を理解しておけば、軽薄なコメンテーターの評論に惑わされることもなく、市民が行うべき役割を息長く続けることができる。政治は、傍観の中には一切ないからだ。「混迷・迷走を深める社会」を目の当たりにしても、民主主義の不確実性を受け入れ、備えを怠らず、市民が政治家以上の闘技のスキルを磨く良いチャンスの到来とみることができるからだ。 |
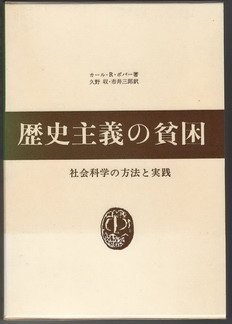 マルクスの「哲学の貧困」をもじって付けられたポパーの名著。すでに日本では1961年に出版されているが、これに出会わなかった日本の若者は相当な回り道を強いられ、苦労が絶えなかったことだろう。(だが回り道と苦労にも貴重な意味がある。脱党・脱会さえできれば、この著作の意味がすぐに理解できるからだ。) マルクスの「哲学の貧困」をもじって付けられたポパーの名著。すでに日本では1961年に出版されているが、これに出会わなかった日本の若者は相当な回り道を強いられ、苦労が絶えなかったことだろう。(だが回り道と苦労にも貴重な意味がある。脱党・脱会さえできれば、この著作の意味がすぐに理解できるからだ。)冒頭に「歴史的命運という峻厳な法則を信じたファシストやコミュニストの犠牲となった、あらゆる信条、国籍、民族に属する無数の男女への追憶に献ぐ」とある。 物理学者だけあり、観測や予測というものが観測者である人間に与える影響を不確定性原理などを引用しながら説明してみせるところなど、今もって、精彩を放つ名著である。 |
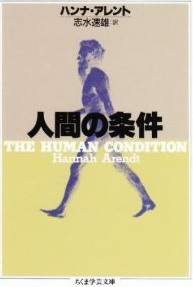 マルクス主義の労働価値説の根本的誤謬を指摘したハナ・アーレントの名著。全体主義を生み出す思想的基盤となった古代ギリシャ以来の人間の諸活動に対する観念について、精緻な分析を加えている。アーレントの『全体主義の起源』(三部作)と併読すると、マルクス・レーニン主義が、ずいぶんと良く出来た独創的なカルト政治思想であることがわかる。また、その影響や変種を含めた雑多なイデオロギーとフレームワークの克服には、特にアジアでは時間を要するだろうし、その間に、社会と人間の荒廃が進行する危機意識はかなり必要だろう。全体主義的思潮の絶えず押し寄せるこの地球で「火の粉」を避けるには相当の頭脳と覚悟がいる。 マルクス主義の労働価値説の根本的誤謬を指摘したハナ・アーレントの名著。全体主義を生み出す思想的基盤となった古代ギリシャ以来の人間の諸活動に対する観念について、精緻な分析を加えている。アーレントの『全体主義の起源』(三部作)と併読すると、マルクス・レーニン主義が、ずいぶんと良く出来た独創的なカルト政治思想であることがわかる。また、その影響や変種を含めた雑多なイデオロギーとフレームワークの克服には、特にアジアでは時間を要するだろうし、その間に、社会と人間の荒廃が進行する危機意識はかなり必要だろう。全体主義的思潮の絶えず押し寄せるこの地球で「火の粉」を避けるには相当の頭脳と覚悟がいる。(ちなみに右掲の『全体主義の起源」では、全体主義が敵を殲滅したあとに凶暴な粛清というテロルを吹き荒らす理由もよくわかる。「全体主義運動は全人類を組織しようとしている運動だから…全面的な“忠誠”の要求を満たさなければ自分は将来の人類そのものから締め出されると考える…」まさに、ロシア革命から、最近のチープな共産党までをも包括している。このマインドコントロールの基礎をなす恐怖支配の自己完結型想念の本質を徹底的に抉り出している) 多少難解だが、昔マルクスを読んだ方は、これを読むと、マルクス読み(但し原典に限る)の人生の時間も決して無駄ではなかったと後悔せずにすむ。マルクスの浅学者がつたないアーレント批判を始めるようになったのは、彼女の箴言を世に問う上で、喜ばしいことだ。マルクスが決して問題提起をしなかった(マルクスがハナから気付かなかった…)問題に深く切り込んでいる。 |
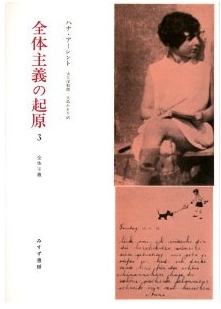 第三巻を最初に読むとわかりやすい。 第三巻を最初に読むとわかりやすい。一節を紹介する「全体を説明し尽くして見せるという全体主義の自負…存在するものではなく、生成するもの、生まれ且つ死ぬものを説明しようとする…すべての歴史的事件を説明し尽くすこと…未来についての信頼できる予言を約束するのである…そのような力をもつイデオロギー的思考は一切の経験から独立し、今しがた起こったばかりのことについても経験によって何か新しいことを知るということはなくなってしまう。…それゆえ、五感…現実から解放される。…」「論理的演繹の自己強制力とは、テロルに支配された運動を発進させ、絶えず活動させるために互いに呼応し、互いに他を必要とし合っている。…テロルが思うまま支配し得るものはもっぱら互いに孤立させられた人々だけであること、だからすべての専制的政府の第一の関心事の一つはこの孤立を作り出すことだ…」 実際に、似非を含めたマルクス主義勢力に没入させられていくプロセスを見事に指摘しているではないか。 そしてこの著作の最後は、非常に深刻かつ困難な人類の未来を前提とした上でも、なおかつ人間の可能性へのポジティブな明るい展望にあふれている。本当の希望というものはこういうことなのかもしれない。人を育てたい、社会に対して真に自律的かつ能動的に向き合いたいと思う方には必読の書といえる。 |
 準備中 準備中 |
準備中 |
| 民主集中制の犯罪 | |
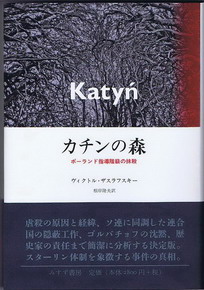 著:ヴィクトル・ザスラフスキー 主題:「カチンの森」副題:「ポーランド指導階級の抹殺」訳:根岸隆夫 発行所:株式会社みすず書房 →ホームページ 発行日:2010.7.9 第1刷発行 2010.10.5 第3刷発行 著:ヴィクトル・ザスラフスキー 主題:「カチンの森」副題:「ポーランド指導階級の抹殺」訳:根岸隆夫 発行所:株式会社みすず書房 →ホームページ 発行日:2010.7.9 第1刷発行 2010.10.5 第3刷発行ソヴィエト体制による驚くべき虐殺の歴史の一端。ソルジェニーティンの「収容所群島」とともに、いまだ十分に明らかにされていない共産主義・全体主義の恐怖政治を理解する上で、必読の書だ。同書の帯にはつぎのように記されている。「虐殺の原因と経緯、ソ連に同調した連合国の隠蔽工作、ゴルバチョフの沈黙、歴史家の責任まで簡潔に分析する決定版。スターリン体制を象徴する事件の真相」 「政府が横暴な場合は、それに対抗する勢力も全体主義的にまとまってよし」とする「全体主義的正義論」≒民主集中制は、目的が別のところにある。つまり自己の組織の支配権を無限に拡大しなくてはならない、というアーレントも指摘するところの全体主義運動の理念である。現在の「党生活者」が自らの偽装のため、スターリン時代を「過去のものとして声高に批判」し、重箱の隅を「清算」する熱心さを強調しても、このエッセンスが維持されれば、完全なスターリン主義である。それは「平和」や「理想的幸福世界」を掲げつつ、無自覚的に世界を復讐主義の連鎖に巻き込むカルト主義思想の梃子である。 |
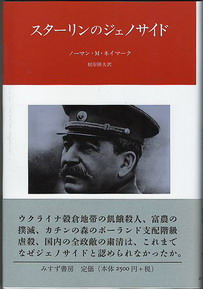 著:ノーマン・M・ネイマーク 主題:「スターリンのジェノサイド」訳:根岸隆夫 発行所:株式会社みすず書房 →ホームページ 発行日:2012.8.30 第1刷発行 著:ノーマン・M・ネイマーク 主題:「スターリンのジェノサイド」訳:根岸隆夫 発行所:株式会社みすず書房 →ホームページ 発行日:2012.8.30 第1刷発行「…スターリンとその取り巻きたちは、このすべてのジェノサイド的攻撃をマルクス=レーニン=スターリン主義の教義に結びつけ、どれもおなじような警察、司法手段、司法外手段を使って実行した。そしてこれにはソヴィエト共産党と国家機構の両方が関与した。ボルシェビキ革命がつくりだした権力と支配の驚くべき実行手段として秘密警察を、スターリンは自分の反対者と想像上の潜在的反対者を弾圧するために動員した。1930年代と40年代はじめのスターリン統治の結果として、無実の数百万人が銃殺され、餓死させられ、強制収容所や強制移住地で死んでいった。今や、この物語はジェノサイド史のなかで大きな一章を割く時が熟している。…」 ボルシェビズムからレーニン主義にいたる共産党の内部統制の別名「民主集中制」のおぞましいエッセンスが未だに大手を振るっているアジア世界で、日本共産党や各国共産党のDNAを考える上で不可欠の書。しかもコンパクトにまとめられている。 ネイマークは、国連ジェノサイド条約が大国の思惑の産物で、政治・社会集団への大量虐殺をジェノサイドのカテゴリーから除外したこと、それによって、今日まで積み残されている深刻な歴史認識上の問題を提起した。この問題は、最近ようやく陽の当たる場所で議論できるテーマとしてあがってきているという驚くべき現実に読者は直面する。 |
以下は、森永ヒ素ミルク中毒事件 歴史文書アーカイブコーナーをご参照。
事件の概要は、以下の文献、及び当サイトの学術論文アーカイブからも、ご覧頂けます。
↓現在の問題点にまで踏み込んだ能瀬英太郎氏のレポート
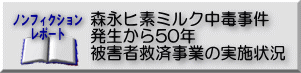
↓能瀬レポート 英語版 (Nose Report)
表向き「公正中立」を偽装して登場した「第三者委員会」が、被害者を無視して
勝手に作った不正な「診断基準」。その文中に使われた「原病」という表現に
ついての解説つき。↓
まだ解決を見ない日本の戦後初の産業公害 PDF:136KB
(著作権Free: 英語教育の教材等ご自由にコピーしてお使い下さい。)
(日本における第三者委員会方式は森永事件以降、常用され、水俣病でも被害の隠蔽に活用されるようになるという要注意なもの。)
↓救済システムでの問題発生を学術的視点からすでに予期している秀逸な論文。
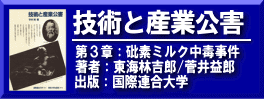

総目次ページへ戻る
トップページへ戻る