13 дах удаагийн хилийн цэргийн бэхлэлтийн судалгаа Олон улсын хамтарсан
эрдэм шинжилгээний баг
Халхын голын байлдааны 76 жилийн ой Монгол Японы хамтарсан олон улсын судалгааны баг
Монгол улсын Хилийн цэргийн дээд сургууль болон Котоёосай Японы судалгааны
төв
INTERNATIONAL JOINT SURVEY GROUP OF MONGOLIA AND JAPAN ON NOMONHAN MILITARY
RELICS
DEFENSE INSTITUTE OF MONGOLIA & JAPANESE CENTER OF RESEARCHING KOTOU FORTRESS
第二次世界大戦 終戦70周年 The 70th anniversary Battle of WWⅡend
2015-16 日本モンゴル共同学術調査を実施
(第13回 国境軍事要塞群 国際共同学術調査団 略称「日蒙共同調査団」)

旧ソ連軍、対日参戦時のモンゴル領内に眠る巨大基地群と貫通する軍用鉄道を確定
【最新報告】
9. ロシア連邦 調査報告【概要へ】
先般、満洲進攻作戦に関してロシアへの調査取材を実施しました。
報道のご紹介
【番組名】『満洲崩壊はここから始まった ~モンゴルに眠るソ連秘密基地の謎~』
ABC Asahi Специальная информационная программа.
"Отсюда начиналось падение Маньчжоу-го.
Загадка замороженных советских секретных
военных баз в Монголии."
放映日:5月29日(日曜)午前 4時1分~午前 4時50分 (49分)
制作:朝日放送(ABCテレビ)(Ch.6)
【番組概要】
70年間闇に包まれていた満州国崩壊に関する新事実。ソ連が150万もの大軍でなぜ侵攻できたのか。モンゴルで見つけた巨大基地跡と極秘任務。元兵士が語る驚愕の事実。
8.調査成果報告 新刊書籍ご紹介

【新刊】お求めはお近くの書店で
『21世紀の戦争論』半藤一利&佐藤優(文春新書)
2016年5月20日新刊
モンゴル国内のソ連軍基地及び軍用鉄道の発見が紹介されました。
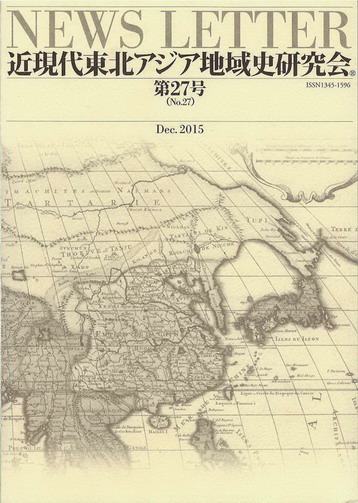
【新刊】
調査成果の要点が「近現代東北アジア地域史研究会」の論文集に掲載されました。
歴史学会の学術報告です。ご注文は、東方書店 まで
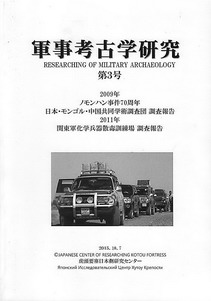
『軍事考古学研究』第3号 2009年ノモンハン事件70周年日蒙中三国共同調査の記録
2011年 中国・牡丹江化学兵器訓練場(第9師団)探査・発見報告
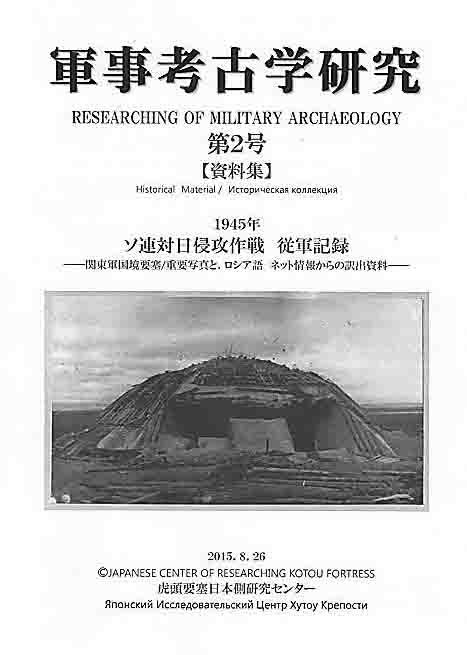
『軍事考古学研究』第2号 2015.8.26発刊(非売品)
ソ連軍制圧下の虎頭要塞41糎榴弾砲の写真等、希少情報掲載
現在、在庫切れにつき増刷を検討中
--------------------------------------------------
2016年ロシア調査報告【概要】
2016年5月、虎頭要塞日本側研究センターは朝日放送(ABC-TV)及び朝日新聞大阪本社とロシア調査取材を実施した。期間は2週間、日本からモスクワへ、モスクワからシベリアのチタへ、チタから再度モスクワへ戻り、5月9日の戦勝記念日を取材し、日本へ帰国するという行程だ。
移動距離はロシア国内だけでも1万キロを越え、6時間の時差を二週間の取材期間内に4回繰り返すという結構ハードなものになった。
調査は多岐に及んだので、要点に絞ってご紹介する。
この取材は直接的には6年前のモンゴル国内でのノモンハン事件戦場現地調査(モンゴル防衛研究所との共同調査)からの継続であり、大きな括りでは8月26日玉砕の虎頭要塞攻防戦をはじめとした1945年の日ソ戦の全体像を明らかにする国境軍事要塞群国際共同学術調査の一環である。(昨年のモンゴル調査は、通算第13回目の調査となる)
満洲国皇帝・溥儀の新情報(タムスク基地を経由した欺瞞作戦)
 |
モスクワ川をへだてて大クレムリン宮殿を望む。
(写真中央の白い建物、中にロシア国会議場が入る)
右端はアルハンゲルスキー聖堂
ボリショイ・カーメンヌィ橋のたもとから、北向きに撮影 |
今回のロシア調査は、昨年のモンゴル現地調査(ページ末尾掲載)から帰国後速やかに開始したロシアのインターネット上の公刊戦史情報の収集分析が基礎となった。長年の懸案であったソ連軍制圧下の虎頭要塞の写真画像入手を手始めに、善意の翻訳者の助力を得つつ、ロシア情報をこれまで得られた知見データに重ね合わせて精査した。東北アジア史の専門研究者の方々からの提供論文、なかでも、ソ連の対モンゴル政策に関する精緻な研究論文は大変な勉強になった。
また、ソ連軍の特殊な塹壕掘削機械といった情報もあった。
そのような中で注目すべき情報として、満洲国皇帝・溥儀の護送隊長の手記が出てきた。
溥儀を奉天飛行場で拘束し、チタまで護送した第6親衛戦車軍・政治将校のA.K.ジェルバコフ氏の証言だ。溥儀護送ルートに関する情報は、日本側では従来、奉天から通遼→チタ→ハバロフスクが定説となっていた。
ところが、ロシア側の情報を精査すると、護送ルートは内モンゴルの通遼からチタへの直行ではなく、モンゴル国内のタムサクブラグ(タムスク基地)を経由していることが分かった。しかも通遼からのフライト時には、チタへの直行が下命されていたが、離陸後、飛行中に突然、航路変更が指示され、モンゴル・タムスク基地へいったん着陸。タムスク基地で機体と乗員をそっくり入れ替えて、チタへ向かい、同市に着陸。その後、市内から16㎞南方の森林地帯にあるモロコフカ(サナトリウム)収容施設へ監禁されたことがわかった。ひょっとして、ロシアではタムスク基地の実態は案外知られているのではないか、そんな期待を胸に、調査を加速させた。
溥儀護送隊長ジェルバコフ氏の手記調査を進めると、モンゴル・タムスク基地への経路変更それ自体が、対諜報作戦の意味をもっていることがわかってきた。スターリンの「溥儀確保」へむけた並々ならぬ決意を象徴するものであった。これは後の極東軍事裁判(東京裁判)において、ソ連軍の満洲侵攻と北方領土奪取を正当化するために意図された政治戦のスタートといえるかもしれない。
我々は、今年にはいって、モスクワ在住のジェルバコフ氏へのアクセスルートを突き止めた。また調査を進める中で、モンゴル・タムスク基地に駐屯経験のある元兵士がチタとモンゴル国境の中間地帯にわずかに1名のみ生存しているらしいことが判明した。しかし、それは数年前の情報で、既に90歳半ば。今年も健在かどうか? 話ができる状態か? その可能性が時間と共に危うくなっていることは明らかだった。
兵士には残された時間がない。急遽、ロシアへ渡航。
10時間のフライトを経て、モスクワに到着した。さっそくジェルバコフ氏の消息を尋ねたが、残念なことに、ご本人は、昨年の秋に他界していることがわかった。「もう1年早くロシアに来ていれば…」無念でならなかった。当時の極秘情報に接した可能性の高い政治将校からの直接証言を取り逃がしたのだ。
 |
溥儀護送隊長、故・A.K.ジェルバコフ氏の
長女・タチアナ氏と、モスクワにて |
だが、更に取材を進めると、ご本人の長女・タチアナ女史がご健在であることがわかり、早速面会をもとめた。タチアナ氏への取材のなかで、満洲国皇帝・溥儀が通遼で最初の取り調べを受けている貴重な写真(本邦初公開)を得ることができた。
溥儀が立ち寄ったとされるタムスク基地について、父親から何か聞いていないか質問すると、回答は「何も聞いていない」だった。だが、彼女は、護送作戦の変更はフライト中に下命され、最高機密レベルの「偽装作戦」であったことを独自の調査から掴んでいた。父親は大戦当時、政治将校であり、戦後も引き続き軍務に従事していた。これらを考慮すると、中ソ対立が続く極東情勢のなかで、満洲に替わって中国を睨む要衝となっていたタムスク基地の実態について家族に語らなかったとしても無理もない。中ソ対立は、共産主義国家同士の武力闘争にまで発展し、核兵器の使用まで検討されていたほど熾烈な競り合いだったからだ。ちなみに虎頭要塞のすぐ北に位置する珍宝島では国境線問題から軍事衝突が発生(ダマンスキー島事件)、中国・人民解放軍側には一千人以上の死者が出ている。
報道http://www.asahi.com/articles/ASJ67732MJ67PLZU00W.html 朝日新聞記事
http://livedoor.blogimg.jp/mmkmuse/imgs/e/c/eca254c3.jpg 紙面画像
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201606200059.html 英語版
タムスク基地の秘匿性の高さが明白に
モスクワでは『ノモンハン戦車戦』の著書で知られるマキシム・コロミーエツ氏に会った。日本側調査団のメンバーである鈴木邦宏氏(「ファインモールド社」社長)の知人で、ロシアの対日戦研究では民間の第一人者である。
 |
『ノモンハン戦車戦』の著者・マキシム・
コロミーエツ氏 |
結論から述べると、コロミーエツ氏は、調査団が制作したタムスク基地の再現図面をみて驚くと共に「第二次世界大戦中に、これほど大規模な基地を構築したとはとても考えられない。60年代以降の(中ソ対立期)ものに違いない」と語った。但し、我々が中間デポと仮称する(マタット基地とタムスク基地の中間にある7km四方の広大な倉庫群)の直列構造の掩体群に関しては、「戦車師団の集積基地の可能性が高い」と、日本側の仮説と同じ見解を述べた。構築時期は別として、ロシアを代表する戦車の専門家としての鑑定だ。
モスクワでは、謎は解明されず。一路シベリア・チタへ
われわれはモスクワから5000km離れたシベリアの軍都・チタにとんだ。チタにはシベリア軍管区の拠点が置かれている。チタ市内には、民間空港のほか、2000m 級の軍用空港が二つある。ドムナ空軍基地、武装ヘリコプター部隊専用の基地。更にチタ南部からモンゴル国境のボルジャに向かって、軍事基地・軍事施設が密集している。チタ市内の移動中にも、対地攻撃ヘリコプターや軍用ヘリが飛んでいる光景をよく目にした。あまり詳しくは書けないが、日本的感覚では想像できないほどの規模と密度で軍事施設が集中している。
 |
チタ市内、まだ氷が残るケノン湖畔をゆっくりと
走るシベリア鉄道の長大な貨物列車 |
チタは人口30万人程度で、盆地となっている。盆地から南に自動車道で抜けると、大型の陸軍訓練基地があり、公道からも見える状態で装甲兵器車両が駐車している。他の兵器車両はどうも倉庫群に格納されているようだ。シベリア鉄道の大型ヤードがいくつもある。まさに中国とモンゴルという、ロシアにとって重要な領域二つに対応できる結節点だ。
モスクワからチタへは7時間のフライトで時差は6時間ある。つまりチタは日本と同じタイムゾーンを採用している。今回の行程を平たくいうと、モスクワについて徹夜明けの作業をしたのち、そのまま、日本へ帰国し、帰国後すぐに徹夜作業に入る、それを終えてまたモスクワに戻る、といったところか…。体内時計が完全に狂ってしまった。
チタの専門家も「不知」
チタではザバイカル国立大学のブーキン准教授と面会できた。
ブーキン氏はシベリア鉄道のモンゴル国内線にいち早く注目していた文化人類学者だ。人間的にも、学術的な意味においても誠実な人だった。日本からいきなり尋ねていった我々を、少々驚きつつも、快く迎えてくれた。ロシアはとかくプーチン政権の強権的な対外政策が強調されるが、国民はとても情緒豊かで、親切。昔の日本人のよさに通じる人懐っこさがある。フレンドリーな国民性なのだ。彼は親切にチタ市内を案内してくれた。
 |
| 日本人抑留者の施設を案内してくれるブーキン氏(右 |
そして、研究の話に入ると、我々の発見したタムスク基地の図面を見て大いに驚かれたが、だからといって、日本側の研究成果に対して安直に同調しなかった。まずは自分の目でしっかり見て考え、断定的意見をさけ、確からしい事象に関してのみ推測的意見を提出するという慎重さがあった。
同氏もまた、「大戦前にこのような大規模な基地が存在していたとはとても信じがたい。ソ連モンゴル相互援助条約に基づき、モンゴルにソ連軍部隊が駐屯したことは知られた話だが、ノモンハン事件後にこのような基地が構築され、1945年に稼働したとは聞いたことがない」と概要このようにのべた。
実はこれは意外な発言でもあった、極東から遠く離れたモスクワの研究者がモンゴルの基地について未知ではあっても、モンゴル国境に近いチタの研究者なら、この基地について何かしら知っているはずだと期待していたからだ。
ところが回答は「不知」だった。ブーキン氏は、モンゴル国内に敷設された狭軌鉄道に関して、「バインツメンからタムサクブラグ(の前線)までの路線がいつ建設されたかはいまもって謎だ」という。また、タムスク基地の再現図面をみて「このような大規模な軍事施設は、第二次世界大戦前では“万里の長城”と“チンギスハンの塹壕”のほかに見たことが無い。中ソ対立のころに、進化した機械を使って構築したのではないか?」と対戦車壕の跡を指で追いながら懐疑的に語った。
我々は今までの知見を詳細に紹介する時間がとれなかったが、タムスク基地で発見した様々な遺物・遺構の写真を提示し、何か気付きの点がないか尋ねた。我々が初めて基地に入った6年前と同じ状態で、先入観なしに写真を観察してもらった。
専門家の鑑定眼
すると、タムスク基地内に今も残る、いわゆる「ジューコフ司令部棟」の写真を見たブーキン氏の手がとまった。ある一点を見つめていた。その後の通訳を聞いて、我々も同感だった。
かれはジューコフ司令部棟の柱の上にしつらえてある装飾に注目したのだ。日本側調査団の中でも
 |
 ブーキン氏が注目した ブーキン氏が注目した
「ジューコフ指令部棟」(上)
その軒下の装飾(下)
2009年撮影 |
これに最初に注目したのがタムスク基地の図面再現を行った山本達也氏だ。三重県の考古学研究者である。「いわゆるジューコフ司令部棟」は、無機質な他の建物とはことなり、装飾が施され、つくりも相対的に古典的だ。ブーキン氏は、この装飾は特徴的であり、フルシチョフ時代の1950年以降の建物ではなく、それ以前の年代の建物の可能性が高いと指摘した。
彼は「この基地は非常に興味深い」といい、今後の研究交流を進めることで合意した。かれは、シベリア抑留記念碑や、日本軍捕虜の収容施設跡、また捕虜が建設したアパートなどの史跡を案内してくれた。鎮魂碑はザバイカル国立大学法学部前の公園に建立されており、「学生が毎日この碑をみているのですよ」と教えてくれた。
モンゴル国境へ近づく
チタでの調査のなかで、基地群内部の建物の年代が次第に明らかになってきたが、それでも決定的な証拠は得られなかった。基地の来歴に関する証言・証拠はいまだゼロの状態である。
我々は、この段階で相当に手詰まりとなった。チタ南方に一人生存者がいるとの情報はあったが、行ってみるまでは真偽の確認のしようがない。しかもチタ周辺は軍事施設が密集している。取材ビザでその周辺を通過できるか自体、こころもとない。もし軍のチェックポイントなどがあればその先はいけない。
 |
満洲国皇帝・溥儀が軟禁されたサナ
トリウム・モロコフカ/チタ(現在
は軍の管理下にある。突撃取材をこ
ころみたが、あえなく撃沈。だが、
入り口を撮影をしても拘束されるこ
ともなく、逆に受付の女性はわりと
親切に対応してくれた) |
また、そもそも対日戦の主力軍・ザバイカル方面軍の元兵士のなかで、モンゴルから出撃したであろう兵士はもはや数名しか生存が確認されていない。だが高齢のため、言語障害が出たり、寝たきりになったりで、昨年からリサーチを続けている間にも、次々と録取対象者がいなくなった。日本と同様ロシアも年齢的な限界をとうに通り越している。生きていても当時の状況を正確に語ることのできる人は皆無に近い。ましてや余りに広大なロシアを、砂の中の針を探すような調査で、どこまで効率的に動くか、という難題がもちあがった。また、なにかしら、腰の引けた対応がいくつかの研究者に散見された。調査対象が過去とは言え、今もロシアが重視する「緩衝地帯」に構築した基地であるゆえか…? 今のロシアの空気を象徴するかのような反応だ。
そうした手探りの中で、ザバイカル方面軍の元兵士がチタの南方150㎞にあるアギンスコエという街に一人だけ住んでいるとの情報を得た。生きていても話ができる状態だろうか。前日まで元気でも、体調が悪化すれば取材は断念せざるを得ない。そのようなケースが続出していた。
とにかく急いだ。チタから専用車をチャーターした。シベリアの白樺並木が続く道を3時間以上走ると、人口2万人程度のモンゴル色いっぱいの町が見えてきた。市内にはラマ教の寺院があり、全体的にブリヤート系の人々が目に付く。
 |
| アギンスコエにあるラマ教寺院のレリーフ |
あらかじめ取材を伝えていたのが、たまたま運よく吉とでた。町を挙げての歓迎ムードであった。首長をはじめ、アギンスコエ退役軍人会の会長が声をかけて、急遽、対日戦従軍者の兵士を5人も集めてくれていた。驚いたことに元兵士たちは、背広姿に一杯の勲章という正装で登場した。どうもアギンスコエという街はシベリア地方でも有数の長寿の街らしい。
まず役所での正式なメダル授与式が行われた。毎年独ソ戦の記念日前後にはこのような式典があるのだろう。今回はチタから派遣されたロシア国営テレビが同席し、日本側からの調査を織り込んだ報道が準備されていた。
結論から述べると、重要証言が得られた。まず参加者は全員対日戦の従軍者だったが、モンゴル国内の基地に駐屯経験のある兵士が二人もいた。取材陣ともに、これ自体が奇跡に近い出会いだと驚き、喜んだ。
それでも、取材となると、大変気を遣った。ロシア国営テレビが同時に撮影しており、市長以下幹部が見守っている。どこまで話してくれるだろうか。事実のみに的を絞って一問一答方式で進めた。まず記憶を鮮明に思い起こしてもらうために全員の氏名・経歴・軍歴を詳しく聞いた。他民族社会で時にはブリッジ通訳となるので、これだけですでに制限時間の大半を消費した。そして後半に基地での目撃証言に的を絞り込んで質問した。
基地駐屯経験者が二人
居住空間に関わる身近な質問からはじめた。居住環境では、兵士は地面に穴をほって、その中に住んでいたことがわかった。風がきつく、穴のなかのほうが快適であるという証言には我々も即座に同意できた。タムスク基地の調査でテントが強風で飛ばされた経験があるからだ。モンゴルの大草原、半砂漠地帯では春先でも、昼間は40度近くまで気温が上がる。一方、夜は氷点下まで下がる。強風でテントの骨組みが折れて潰れたり、テントごと吹き上げられてしまったり、と散々な目にあう。昨年の現地調査では、マイクロダウンバーストだろうか、深夜、地表面が異様に暖かくなったかと思うと、突然、猛烈な風が吹き付け、テントが二棟全壊した。
 |
マタット基地の対戦車壕の来歴を証言した
アナンダ・バタエフ氏(左) |
各基地のグラウンドレベル以下に掘られている穴の多くは、地下式の居住施設であることが分かった。「ゼムリヤンカ」というこの施設は、二人一組で兵士が掘るが、彼らが基地についたときはすでに掘ってあったという。これは何気ない証言に見えるが、実は重要な意味をもっている。
ともかく、兵士は煉瓦とモルタルづくりの立派な建物に住むことはできなかった。我々はゲル様のテント生活かと想像していたが、地面の下に住み、水平に近い板に干し草をまぶした天井(蓋といったほうがいいか?)で覆ったという。完全に穴倉生活だ。でもそのほうが半砂漠地帯の環境では快適なのだ。
彼らは、戦車や大砲などは戦闘行動開始になるまでみることができなかったという。この証言は整合性がある。最新型戦車が工場から侵攻直前に集結したことが知られている。マタットとタムスクの間の、仮称「中間デポ」に第6親衛戦車軍の最新型T-34戦車が配置されたらしいことは確かだ。
重要情報=巨大基地の来歴が判明
対戦車壕について知っていることはあるかと聞いた。すると驚くべきことに、総延長36㎞、幅7m、深さ3mと正確な数値が、さらさらと証言された。更に1941年から1943年にかけて対戦車壕が構築されたとの重要証言を得た。もっとも知りたかった基地建設開始の時期が、質問もしないのに、兵士の口からあふれ出てきた。この年号は先輩兵士からの伝承のようであり、極めて信憑性がある。日本でもそうだが、兵士は自分達が寝起きする陣地の来歴については、意外に詳しいものだ。
なお、対戦車壕が深さ3mということはすでに1mほど砂で埋まっているということだ。逆に幅は7mであったということは、砂漠の風化で広がっている可能性もある。
タムスク基地のジューコフ指令部棟の機能が判明
さらに驚くべきことに、スターリングラード攻囲戦を経験し負傷経験のある兵士・サンザヤ氏が、タムスク基地のいわゆる「ジューコフ司令部棟」の役割について明快に答えてくれた。「これは、第6親衛戦車軍の臨時参謀本部で、将官らが会議を開く建物だった」。あまりに明快な答えに少々たじろいだが、仮説を裏付ける重要証言を得ることができた。
そのほか、兵士からは「共同のサウナがあった」、「食料は一日三食十分に与えられていた」と、かなり恵まれた待遇を得ていたことがわかった。大兵力の集積に加え、その兵員の胃袋を満たすための膨大な物資の集積が行われた事実が次々に証言された。話が盛り上がって、地面に空いた穴の細かな質問に移りたいと思ったとたんストップがかかった。
確かに非常な高齢ということもあり、健康に配慮して断念せざるを得なかった。
だが、基地来歴に関する情報が直接証言で得られたことは大きな意義がある。
ロシア国防省・軍事公文書館の対応
モンゴルの巨大基地が1941から構築が始まり、1943年ころには完成の領域に達していたことが明らかとなった。対日参戦準備は片時も休むことなく進められていたことがほぼ確定した。それを裏付ける文書が欲しいところだ。ロシア国防省・軍事公文書館に正式なルートで情報公開を請求したが、残念ながら回答自体がなかった。
国立収容所博物館・館長
「2千万人が強制収容所送り、うち4百万人が犠牲に」
今も続くスターリン粛清犠牲者の苦悩
ソ連の独ソ戦、対日戦を含む二次大戦の全過程はそのまま、スターリン粛清の歴史でもある。それは、ソ連軍の軍事行動にも多大な影響を与え、捕虜収容所・抑留政策につながっている。溥儀拘束から収容、その後の監禁に関して情報を得るべく、モスクワに戻って、国立収容所博物館のロマン・ロマノフ館長(33歳)にインタビューした。だが、そこで知ったのは想像を絶するスターリンの自国民への大虐殺の実態だった。
館長によると、スターリン粛清で強制収容所に送られ虐待された人々は約2千万人。しかも収容所の実態は、ソルジェニーツィンの著作『収容所群島』などで知られているよりも、はるかに過酷であったことが判明しているとのことだ。
北極海直近の地の果てにそびえる人跡未踏の大山脈の頂上に大規模な強制収容所がつくられた。その空撮映像が館内に流れていた。背筋が凍る光景だ。日本人の常識をはるかに超えている。まさに、才能豊かで、誠実で、良心的な人々が腐敗した独裁者側近から狙い撃ちにされ、家畜以下の扱いで殺された。この虐待による死亡者は少なくとも400万人。「2千万人が強制収容所に送られ、そのうちの20パーセントが帰らぬ人となった。処刑による死者は70万人である」
だが、実際の犠牲者規模は不明な部分が多く700万人死亡説もあり現在も追跡調査が続けられている。独ソ戦での犠牲者に匹敵する規模の弾圧、ナチスのユダヤ人虐殺に匹敵する規模の殺戮が、「人民の敵」のスローガンと共に、共産党独裁政権のもとで実行された。
スターリン崇拝へと「先祖返り」する共産党
最近配信された驚きの報道写真がある。ロシア主要野党の一角を占めるロシア共産党が再び「スターリン崇拝」を始め、党首がクレムリン前に残るスターリンの石像にお辞儀をしている姿だ。歴史が逆回転をしている。かつての「スターリン批判」はどこに消えたのか。共産党の本質を示す象徴的な「先祖返り」だ。あるモスクワ市民は「今の議会内に本当の野党はいない。みんな現政権の応援団だ」とつぶやいた。日本的にいう「大政翼賛会」か? しかも彼によると、「スターリンがいなかったら果たしてロシアは独ソ戦に勝てたか」なる言説が、最近、まことしやかに登場しているらしい。
ロマン・ロマノフ館長はこの風潮を一刀両断にした。
「スターリンはすべてを誤りに導いた。独ソ戦における勝利はスターリンの功績ではない。国民が戦った末の結果だ。スターリンは赤軍粛清などで犠牲者をいたずらに増やしただけだ」。
博物館には「スターリン信奉者」が押しかけることもあるらしい。
館長は、「(歴史の継承に)反対する人もいるが、それへの対応は困難のうちには入らない。弾圧の歴史は学ぶ必要がある。(そういう人々には適切な)教育をしなければならない。」と静かに語った。
実際、未だに多くの強制収容所の犠牲者とその遺家族が深刻なトラウマに苦しんでいる。博物館では心理カウンセリングを兼ねた歴史継承の座談会が定期的に取り組まれている。
溥儀の収容に関しての新情報は得られなかったが、スターリンの戦争指導に関してようやく聞き取れるようになってきたロシア人の解釈を学ぶ大変貴重な機会となった。一部の向きに見られる「独裁ゆえの勝利」という軽い捉え方は、戦争を取り巻く複雑な事情を切り捨てることになり、注意が必要だ。このような現状をみるにつけ、複雑で凄惨な歴史的背景を抱えるロシアとは、市民同士の誠意をもった交流を粘り強く積み重ねていく必要を感じた。
スターリン粛清の本質
話はそれるが、スターリン粛清の本質は、経過だけをみていてもわからない。例えば赤軍粛清の象徴であるトハチェフスキー事件をスターリンの個人的逆恨みなどで説明する人もいる。或いは大国由来という説に腐心するマルキストもいる。一面の要素や動機のひとつではある。だが、日本国内でのマルキストによる「粛清」をじかに体験・見聞し、その起源を探り続けている人々の意見を参考にすると、唯物史観の歴史主義的「優生思想」に起源があるといえそうだ。レーニン・スターリン両主義はその派生物に過ぎない。
日本でも入念な計画のもと、支配セクター内部では、ためらいもなく、デマ、監視、査問、隠蔽できるとみるや数を頼みの罵詈雑言から(時には)拷問まで、秘密警察ばりの言論・人権弾圧を実行してきた。
その背景にはイデオロギーの魔力がある。即ち、自らの集団を「外部世界からの絶滅圧力にさらされている」なる脅迫観念で結束させ、他方共産党内部で「異端」判定された「批判」は一転、外部の「敵世界」と同じ「絶滅すべき歴史的な劣等思想」「到達すべき理想への反動」と定義できる。これが頭の中の四畳半を回り続け自己完結する。党「神殿」奥深くの「異端審問」で詭弁論に長けた部隊が再生産されつつ現場に出動し、現場には「前衛党を批判する反動分子」という単純で扇動的な解釈を刷り込む。ヒトラーのいう “愚鈍な大衆は知的水準を下げた反復宣伝を結局受け入れる” とのプロパガンダ思想と同根だ。紅衛兵の狂気から大虐殺へ移行した文化大革命、ポルポトの大虐殺等々に共通する。もちろんマインドコントロールの一変種でもある。だが、権力掌握後に支配組織内部のどちらかというと「味方」に対して行われるジェノサイドが桁違いの規模にエスカレートする背景には、このイデオロギーに固有の全体主義的特性があると思われる。
歴史主義的「優生思想」の罠は形を変えて存続
「理想国家」なる単一の国家主義的アイデンティティへの帰属意識の強要と「歴史発展段階において劣等的位置にある外敵」からの脅威を刷り込む点。これはナチズムとさして変わらない。異なるのは、排外主義的民族主義での拡張主義を第一義にするか、理想郷プロレタリア独裁国家を第一義にするかの違い。両方とも「主役」が異なるだけの国家主義である。その「主役」は、権力の座にある(或いは、権力を目指すべき)「前衛党」が「認定」するのだから、自己撞着的な循環理論となる。「一神教」と揶揄される所以だが、当の思想家は「科学」を自称し究極の理想社会の代表者と自己規定するので、状況次第では、異論の暴力的封殺にもためらいをもたなくなる。「無限に世界に流布せねば前衛党は敗北する」との想念は、拡張主義の思考パターンに通底し簡単に入れ替わる。
ISの回路も似ている。「カリフ制イスラム国家の理想」を第一義にし、無限の拡張主義が想念となり、世界に「劣等文化圏殲滅用反乱支部」(テロネット)を構築して「ソ同盟防衛」ならぬ「IS防衛」をさせ、内部での粛清にも精を出す。もちろん、フタをあけると、腐敗した人間集団が独裁支配で閉ざされたコミューンの中で現世の利益を享受しているだけなのだ。徹底したデマで武装され、一度に説明されてもなかなか理解し難しいゆえ、「表看板」を真に受ける若年不満層をとりこにしやすい。この罠は昔から身近に存在し、条件が揃えば、ある日突然キバをむく。
強烈な猜疑心にとりつかれたスターリンをソビエト社会が容認し、結果的に変容された国家主義に拍車をかけたのは、歴史主義的なイデオロギーの特性と見る。この後遺症は未だに深刻だ。
5月9日、モスクワの独ソ戦・戦勝記念軍事パレード。厳戒態勢
元兵士を一人でも多く探すため、5月9日の戦勝パレード会場にも参加した。だが、式典には一般市民は参加できない。パレードのメイン会場である赤の広場周辺から完全に締め出される。さらに広場は一回り広域に封鎖され、「緩衝地帯」がつくられる。これぞロシア的発想か? 市内中心部に通じる出入り口には、大型の重量車両をかき集めて「バリケード」をつくる念の入れようだ。市民がパレードを沿道から眺めるという風景は無い。
 |
市民を締め出して実施される軍事パレード。
グム百貨店の屋上に配置された狙撃チームの一人。 |
会場となった赤の広場内部は、更に厳重な警戒が敷かれていた。プーチン大統領が座る主賓席は両サイドに巨大な囲いを置いて、退役軍人家族ら招待客からも視界が遮断される。その招待客席の前に陣取った報道機関の前には警護隊がずらりと並び、一段あがった報道席から足を一歩でも広場側の地面に着けようものなら即刻厳しい注意が入る。広場の向かい側に位置するグム百貨店の屋上には狙撃手用の鉄骨製ポストがこれ見よがしに設置され、無線交信用ヘッドセットをつけた兵士が消音器つき狙撃銃を少なくとも三方向に向けている。うち二つの望遠照準器は広場の外、既に立ち入り禁止となっている緩衝地帯を探っている。さらにその銃口の一つは厳格な審査を経ている我々取材班の方に向けられていたのであるから、その警戒心たるや尋常ではない。
5月で終わっているロシア人の大戦観
全般的印象からみると、ロシア人にとって、第二次世界大戦は1945年5月9日で終了している。その3ヶ月後に満を持して決行された対日戦は、1ヶ月あまりで決着がついたので、ロシア国民の印象のなかではその存在感が非常に薄い。実際、退役世代からは、「中等教育では満洲侵攻は教えられなかった」との声が聞かれた。つまりロシア人の歴史感覚のなかでは、日ソ戦は、“知らないことはないが”…、事実上「忘れられた戦争」に近い
 |
| 赤の広場を行進するロシア軍兵士 |
。シベリア在住の戦争体験者の証言がいままでほとんど外に出てこなかったこともわかる気がする。
だが、満洲侵攻作戦は、ソ連軍の独ソ戦での経験知が高度に結集された完成度の高い作戦である。全縦深同時制圧理論の教科書的な展開といえる。日本軍の瓦解速度があまりに速かったことや、傀儡国家ゆえか、無責任主義ゆえか、在留邦人を日本側がいとも簡単に見捨てて遁走したことがそれに拍車をかけた。自らが招いた恥ずべき結果を直視しなければ、多くの同胞の犠牲と戦争経営の全体像─それは即ち当時の政治と不可分だが─への認識は当然おかしなものになる。日本の敗戦はソ連の参戦で促進されたという側面を忘れれば、対米関係も実のところ理解不能となる。反米や親米という二項対立にさいなまれるだけだ。
だが、この国は、原爆1個分を越える大陸での同胞の犠牲、(アジアの民の犠牲はそれに百倍するという事実)に目を背ける努力を不断に続けている。そのツケが、日本人の歴史認識のいびつ化につながている。様々なイデオロギーの制約から、東北アジアの歴史的経験をグローバルな視点から再検証することも遅れている。現在の複雑な世界を解釈する能力が「単純思考へ収斂」されていくきらいがある。大きな教訓を摂取するチャンスを、この数十年間みすみす逃してきたのではないか。
ソ連軍の戦備
対日戦はソ連軍の圧勝で終わったので、さぞソ連軍は物量だけにものをいわせ、従って日本軍は元から負ける運命だったと単純に考えがちだが、これはある種の短絡を含んでいる。
ソ連軍は、もちろん、勝算はもっていただろうが、「張子の虎」となった日本軍をも、決して甘くみてはいなかった。これが戦争のリアリズムだ。モンゴルの巨大基地群はそれを立証する象徴的存在だ。少なくとも4年間、対日戦備を片時も休むことなく続けていたのだ。
ソ連軍は「窮鼠猫を噛む」の諺を忘れていなかった。もともとソビエト労農赤軍のドクトリンは超攻撃的である。独ソ戦直前には、ソ連側からドイツに侵攻するシミュレーションを描いたりもしていた。国内的にはレーニンもスターリンも、自称「人類の理想」に反抗するものは「人民の敵」として容赦なく徹底的に殺戮・殲滅した。それがロシア革命の現実であり、革命に伴う鎮圧作戦(国内内戦)の実際である。
独ソ戦を通じて、この攻撃的ドクトリンは縦深理論として成長していった。対満洲侵攻作戦では、ソ連軍は関東軍を包囲殲滅する陣形をとっている。ワシレフスキー曰くの「極東にカンネーを再現せよ」だ。極端な言い方をすると、一人も生かして返すな、という決意である。ソ連は西部方面(ヨーロッパ方面)の覇権が維持できるだけの戦力は残し、兵員を東部戦線(シベリア・極東方面)に大量移動させた。とくに独ソ戦での歴戦の兵士と、山岳線に熟達した兵士だ。これらが、困難な大興安嶺山脈越え作戦やアムール・ウスリー渡河作戦完遂のカギになった。ザバイカル方面軍では対満洲作戦に旧式のBT戦車も大量に動員している。
だが、日ソのあまりの戦力差にのみ目を奪われてはいけない。1939年、日本が満洲国を建設してソ連と境界を接し、ありきたりな国境意識(それは日本だけではないが)から、安易な軍事行動を開始したノモンハン事件は、ソ連にとっても許し難いものだった。モンゴルの警戒感も極度に高め、巨大な兵站地を確保できたことで、ソ連側の将来にわたるシナリオを完成させた。関東軍は「ソ連を懲らしめる」といいつつ、逆に、“忘れた頃”に「ソ連に懲らしめられて」しまった。犠牲になった人々の苦しみはいかばかりか。
だが、いかんせん、この「威勢がいいだけの思考方法」は軍隊というより、どちらかというと、民間政治家の大きな困りものの習性だ。
もちろん、自分の手柄ほしさに仲間を死なせて憚らない「威勢がいいだけの将官」が有事になると湧いて出てくる。「戦争」中毒となった軍事官僚である。それを現場主義者と未だに評価する呑気な人がいるらしい。見渡す限りの死体の山のひとかけらに自分がならないと、その痛さやむなしさがわからないようだ。ノモンハン事件では、そういう参謀が何人も跳梁し、責任をとらず、その後の太平洋戦争で多大な兵の犠牲を強いた。そして、そんな「傲慢将官」が指揮するとたいがい最後には負ける。(その視点からノモンハン事件や満洲侵攻作戦をみると腑に落ちる。)
 |
ボリショイ・モスクヴァレツキー橋よりポクロフスキー聖堂
(ワシリー寺院)を望む(北北西方向へ撮影)
左奥がグム百貨店、その正面が赤の広場
 
モスクワ川にかかるボリショイ・モスクヴァレツキー橋は、
2014年2月27日、元第一副首相で野党指導者ボリス・ネム
ツォフ氏が暗殺された場所。今も献花が絶えない。 |
国際政治は複雑怪奇…
ノモンハン事件では、ソ連は日本側以上に多大な犠牲をだしながら、かろうじて勝利した。だが勝って満足しておわりだろうか? そんなことはスターリンには関係ない。「一戦交える」とは、力で優位に立つ側に、有事の際、「百倍返しをするまたとない口実を半永久的に与え」続けるだけである。百年たっても繰り返される復讐戦の火蓋を切って落とすことになる。少なくとも、そうすると決めたソ連の独裁政権がずっと隣に控えて居たのだ。だが、そのすぐ隣へと、傀儡国家を作ってわざわざ近づいて行った日本にも、結果への大きな責任があることは言うまでもない。もちろん、今後日本が再び「満洲国」を作るようなことは考えにくい。だが歴史への振り返りがおろそかになることのリスクは、世界を解釈し、態度を決定していく上で、その思考方法が昔どおりに単純化される危険性があるということ。これは、いわば万国共通の落とし穴だ。
当時のヨーロッパの政治軍事状況を理解することはどの国にとっても難しい。世代交代が繰り返されるに従って戦争への生々しい痛みの感情は薄れていく。だが、痛みがあるといっても人それぞれであり、印象が鮮明だからといっても、現世の生活があり、解釈困難な問題、決断に迷う問題が無限にある。実際ヨーロッパも未だに、自らの後姿に目を背ける人も多いし、歴史への解釈は迷いの途上である。だが、かつて日本に「欧州政治は複雑怪奇」と言いつつ政権を放り投げた政治家が居たことも忘れることができない。島国的視点から世界に武力でうって出て、あっという間に思考停止し前後不覚に責任を放り出し惨めな結果を招いても知らぬふり…。大勢の無辜の人々が理不尽な扱いを受け、おびただしい血であがなわれた貴重な教訓を忘れるわけにはいかない。
ロシアを旅して…
日本は戦後、冷戦構造の中で、欧米との関係を思考することに終始してきた。要するに、あまり世界を切実かつ真剣に考えなくてもいい環境に甘んじてきた。
ロシア人も同様に満洲とその崩壊を導いた日ソ戦の記憶から、すでにはるか遠ざかっている。このような状況のなかで、北方領土問題だけが定期的に回想される。両国民とも領土意識という民族感情だけを時折ぶつけあって、なにかしらお互いに「片思い的」なメッセージを送り続けてきたということだろうか。もうそろそろ、大人の会話ができる年頃になってもいいと思うのだが、どうも現実は逆の方向にも行きかねない危うい状況だ。その要因の一つには、両国が極東におこった過去の痛みを忘れ、事実を直視せず、様々なイデオロギーがバランスを欠いた都合の良い歴史解釈に走って対立だけを煽り、かつての「欧州政治の複雑怪奇」の中での立ち回りを再検証することを避けてきたことに起因していると思わずにはいられない。これを続けていると今後も同様に「複雑怪奇
」に振り回され、単純で「血わき肉おどる」短兵急な手段に走る状況が到来しないか? それが唯一の気がかりだ。
謝辞
最後に、朝日放送取材チームと関係者の皆様、朝日新聞大阪本社はもとより、テレビ朝日モスクワ支局、朝日新聞モスクワ支局、大学及び研究機関の専門研究者の皆様、近現代東北アジア地域史研究会の皆様、通訳・翻訳者の方々、中でも昼夜を問わず精力的な支援・アドバイスを頂いたサリュートメディアサポートの皆様に衷心より感謝を申し上げたい。多くの方の助力があって、初めて実現した国際的な協働作業だった。考え続けることの大切さ、難しさ、そして楽しさを私たちにご教示くださっている多くの関係者の御厚意に改めて感謝しつつ、今報告を締めくくりたい。
このページのトップへ戻る
---------------------------------------------------
7.朝日新聞DIGITAL で大型特集スタート 2015.8.19-
yahoo地図のタブから画像をクリックすると動画スタート。
(動画・写真データが豊富、朝日新聞社機「あすか」&
地上踏査班によるドローン空撮映像がご覧になれます)
Stalin's secret railway for war against Japan confirmed in Mongolia:
by the Asia & Japan Watch(AJW)
-------------------------------------------------------------------------------
【報道のご案内-時系列-】
1. 朝日新聞 朝刊 全国版1面にて報道 2015年6月11日
朝日新聞DIGITAL 第一報 記事及び空撮映像(VTR)(無料登録で視聴可能)
朝日新聞DIGITAL 大阪本社版 35面追加記事
2. 朝日新聞【夕刊】全国版1面にて続報掲載 2015年6月11日
朝日新聞DIJITAL 全国版で続報掲載 (写真増強、開拓団の悲劇紹介)
3. The Asahi Shimbun WEB国際版に、英字記事が掲載されました。
http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201506110056
“Stalin's secret railway for war against Japan confirmed in Mongolia”
4. 6月13~23日
TV特集ドキュメンタリー全国放映決定 ANN系列「テレメンタリー2015」にて
タイトル:「シリーズ戦後70年(5) 満州に進撃せよ!~草原に眠るソ連軍巨大基地~」
 現在、このサイトで録画が流れています
現在、このサイトで録画が流れています
→http://www.dailymotion.com/video/x2u5lc2
(終端が少し切れ)
5. プレ企画↓【既報】 2015年5月7日-12日掲載済み 朝日新聞 夕刊全国版 5回連載シリーズ
 pdf 2.54MB「敗北の序章 ノモンハン」№1-5
pdf 2.54MB「敗北の序章 ノモンハン」№1-5
6. テレメンタリー2015、年末総集編で再放送(2015年12月)となりました。
(以下、新着順にトップへ掲載)
-------------------------------------------------------------------------------------------
調査報告【概要】
はじめに
2015年4月24日から5月8日の15日間、虎頭要塞日本側研究センターとモンゴル防衛研究所との共同で、第二次世界大戦終戦70周年(ノモンハン事件76周年)を記念して、「日蒙共同調査団」が組織され、踏査総距離3000kmに及ぶモンゴル東部エリアの共同学術調査が行われた。
これは、6年前の2009年実施調査以来の延長線上にあるもので、3回目の現地調査となる。
今回は、1939年に発生したノモンハン事件からその後6年間にわたるソビエト・スターリン政権の対日侵攻作戦計画の実体を解明するという問題意識から、その実証研究として、同国・東部国境地域に構築された大規模なソ連軍の補給基地とそれらをつなぐ軍用鉄道の実態、その建設時期についての現地調査・文書調査を行った。1945年8月9日、156万人の大兵力で満洲に侵攻し、満洲国を崩壊に導いたソ連軍の主力・ザバイカル方面軍の兵站の実態であり、これまで殆ど関心が払われてこなかったテーマである。
ちなみに、当センターは、2009年にモンゴル外務省で行われたノモンハン戦争シンポジウム(モンゴル内閣府主催)で、「ノモンハン事件は第二次世界大戦を1939年9月に惹起させる誘因の一つとなったとも言える大戦争で、世界史的にみて極めて重要な位置をしめるもの」との視点を提起した。近年でも、米国のスチュアート.D.ゴールドマン氏や、英国のアントニー・ビーヴァー氏など、欧米の歴史学者が先行する形で、同様の視点からの研究が進んでいる。
1939年に発生したノモンハン事件。旧満洲国と外蒙古(モンゴル)の国境線をめぐる紛争の過程で、「ソ連をこらしめる」としながら関東軍は感情的に戦闘を拡大した。「満蒙は日本の生命線」をスローガンに、対外権益を「日本人の生命財産の安全にとって死活の地域」と設定して大陸進出政策を実行した。その対外政策から必然的にもたらされた、いわゆる「国境線を巡る帝国軍隊の大言壮語の火遊び」がノモンハン事件である。日・ソ蒙軍あわせて4万人以上の死傷者を出した大戦争だったが、日本はこの戦争の実態を、国民の目から完全に隠蔽した。中国大陸への侵略の過程で傲慢となった軍の体質、そして、その後の太平洋戦争の全過程に通じる過ちの原点ともいうべきものが、この戦争に隠されている。
この「ノモンハン事件」でのわずか数ヶ月間の経験を通じて、スターリンは日本軍全体の弱点のみならずソ連軍の問題点をも把握し、一気に戦列を建て直した。結果、奢り高ぶっていた関東軍はソ連軍に逆手をとられることになる。
 |
| 東部国境めざし砂漠のオフロード地帯を走行中の調査団車両 |
第二次ノモンハン事件以降、一種の総力戦として戦略的攻勢に転換したソ連軍によって、両軍は莫大な犠牲を出しつつ、日本は敗北を喫した。スターリンがノモンハン事件を通じて学習した戦訓と、日本への警戒心・復讐心は、その3年後、1942年スターリン秘密指令(今回発見文書)として、対満洲攻略作戦に決定的な補給支援能力を発揮するモンゴル東部の長大な軍用鉄道建設へ結びついたことになる。そしてその3年後の1945年8月、「日露戦争まで遡って日本に奪われた領土を奪還する」と決意したスターリンの「満洲包囲殲滅作戦」により、モンゴル東部国境タムスク基地を拠点として出撃した主力・ザバイカル方面軍は電撃的かつ短期日で満洲国の首都を陥落、関東軍の総崩れをもたらした。結果、20万を越える在満邦人の犠牲が生み出された。その歴史の痛みは、いまもって十分継承されているとはいい難い。戦車で開拓民を蹂躪し、ジュネーブ条約違反のシベリア抑留で捕虜を虐待したソ連軍も非道であるが、その前提に傀儡満洲国の存在があったことも忘れることはできない。
関特演(関東軍特種演習)なども含めて日ソ両国にいえることでもあるが、ソ連軍もまた、国際条約の精神を守ることなく対日侵攻作戦を準備し続け、そし実行に踏み切った。ソ連スターリン政権は、自国防衛の都合から日中戦争の泥沼化を背後で画策・扇動していたふしもある。マルクス・レーニン主義を支柱としながら、コミンテルンを手足として利用し、歪んだナショナリズムを成長させながら領土保全と対外拡張政策を進めた。一方、国内では独裁者に群がる集団の利権と権力闘争を極限まで加速させた。当然の帰結として、自国のみならず衛星国にも「人民の敵」のレッテルで無実の人々を大量虐殺するという「粛清」の嵐を吹かせた。
一方、日本は、ノモンハン事件で経験した国境紛争の愚を忘れる形で「対ソ」の「北進論」から豹変し、あっというまに米英とことを構える「南進論」へ傾倒し、太平洋戦争に突入した。
ノモンハン事件では、辻正信・服部卓四郎の両参謀に代表される作戦指導者らは、陸軍中央の制止も統帥権をも無視し無謀極まりない作戦を強行した。その後、敗北の責任を部下に転嫁し、自決まで強要しつつ口封じをした。
陸軍中央も政府もまた、複雑な国際政治を見極める能力に著しく欠如し、外征軍である関東軍の暴走を抑止する気概も能力もなかった。結果彼らは、まともに処断されることもなく、逆に太平洋戦線で見事に「復活」した。その後の主要作戦で懲りない指揮を繰り返し、兵の残酷な消耗と大敗を導いた。
にも関わらず、彼らの中に本質的な反省は見られず、戦後、国会議員にまでなって政界で跳梁したものさえいる。これらの歴史が教える教訓は、すぐれて今日的な意味を持っている。
2015年調査のテーマと結果概略
今年はモンゴル領内にソ連軍が構築した巨大な兵站基地3箇所+1箇所を貫通する大動脈、総延長1000km弱に及ぶと見られる軍用鉄道の実態に迫ることであった。もちろん、3基地を再度細部にわたり観察すること、ノモンハン事件の戦場をより多角的に観測することも含まれている。モンゴル防衛研究所での文書調査もあわせて、15日間という長丁場の行程となった。
今回の調査は、従来の調査の中でもっともハードなものとなった。鉄道の軌跡を示す盛り土の経路は、道路(轍-わだち-)とは無関係に存在しており、湿地帯が入り混じる半砂漠地帯のなかで、目印もなく、轍さえ存在しない完全オフロードを、GPS装置とコンパス、旧軍の座標地図などを唯一の頼りとして、不規則に移動しなくてはならなかったからである。半砂漠地帯では、突然湿地となる軟弱地盤に車両が入り込みスタックすることがある。轍は砂漠での車両走行可能なルートを示す目印であり、これから外れることはベテランのドライバーにさえ、大きな負担と緊張を与える。
調査ポイントはあらかじめ、45箇所をピックアップしたが、予想以上に時間がとられ、半分以下に絞り込まざるを得なかった。だが、困難を乗り越え、鉄道施設の存在を裏付ける様々な態様の物的証拠を入手でき、調査は成功した。軍用鉄道の全体像の70%程度、主要部分の構造を実証的に確定できた。(詳報別途)
 |
| モンゴル上空を空撮中の朝日新聞社ジェット機 「あすか」. 地上班撮影 |
なお、これらの調査計画に加え、無線操縦ヘリコプターからの低高度撮影や、朝日新聞社所有ジェット機「あすか」による高高度からの航空撮影がミッションに加わった。特殊な機器の海外への持込でもセキュリティとの綿密な協議が必要となったし、モンゴルへのジェット機の乗り入れでは、事前の事務調整作業が膨大な量に達した。
地上踏査班もまた、砂漠での彷徨を避けるための緊張と努力を絶えず強いられることになった。実際に、強化仕様の4輪駆動車でさえ、そのトラブルは頻繁となり、砂嵐、竜巻、熱射と吹雪という気候の激変に巻き込まれ、調査隊員の疲労はこれまでになく高まった。季節的に、脳炎ウイルス保菌の5ミリ大の吸血マダニが大量に発生し、ほぼ全員が連日とりつかれる事態となった。感染症の危険に晒された。
航空撮影班・カメラマンもまた、空中での強烈なGの重圧に耐えながらの撮影に挑んだ。朝日新聞の6月11日付け朝刊の1面を飾った巨大基地・マタット基地の全景は、世界初の空撮映像であり、旧ソ連軍の対日参戦時の後方補給能力及び作戦計画の隠されてきた実態を赤裸々に示す第一級の歴史資料となった。世界的にも貴重な知見を提供してくれる写真だ。70年以上にわたって変わらず存在し、それぞれが、東京・山の手線がすっぽり入る長大な対戦車壕で防備された巨大基地だ。高高度からの撮影でも、最遠部は、地平線の彼方まで続き大気に霞んでいる。満洲国を崩壊させたソ連主力軍の出撃用で、軍需物資を高度集積させた基地である。1945年8月9日以降、満洲国を一気に崩壊に導き、同時に在留邦人の筆舌に尽くし難い悲劇をも生み出した軍事行動の背景がここに隠されている。この1枚の写真には、これまでの日本人の歴史認識のみならず、第二次世界大戦末期の極東戦線における歴史認識を大きく塗り替える情報が詰め込まれていると言っても過言ではない。
なお、安全運行への緻密な配慮はもとより、事前の綿密なフライトプランの策定作業に加え、現場では座標データを唯一の頼りに、気象条件に大きく左右される有視界飛行で地表遺構を探す困難に挑んでこれを成功に導いた「あすか」クルー及び航空関係者の皆様の努力には驚嘆するしかない。
また、このミッション自体が、モンゴル航空当局の全面的支援があって初めて可能となったものである。両国の架け橋となって調整業務をこなしてくれたコーディネーターにも敬意を表したい。
なにより、日本側の取り組みに対して、モンゴル国の航空を含めた関係者が大いなる関心と敬意を払ってくれた。特筆すべき国際的な共同作業となった。ノモンハン事件で日本がかつて血を流して戦った敵国と今日、このような共同研究ができるまでになったことは、それ自体、両国国民の平和共存へ向けた強い願いの現れであり、歴史認識への相互理解へむけた実践努力の進展を示す証といえるのではないだろうか。
----------------------------------------------
【名称】
第二次世界大戦終戦70周年 日本・モンゴル共同学術調査団
(=第13回 国境軍事要塞群 国際共同学術調査団)
【渡航調査期間】
平成27年(2015年)4月24日~5月8日(15日間)
【調査範囲及び調査箇所】
モンゴル東部国境地域の旧ソ連軍基地4箇所と鉄道幹線及び支線、ノモンハン事件戦場
首都ウランバートルにおける証言及び文書調査
全行程15日間 モンゴル国内移動総距離 約3,000km
【参加者】 地上班総員15名 航空班総員6名以上
【専門分野】
軍事考古学者、戦史研究家、兵器鑑定家、歴史研究者、朝日新聞本社取材班、朝日放送取材班、調査コーディネーター他
【派遣事務局】
JCR-KF虎頭要塞日本側研究センター
(本部:岡山市 首都圏本部:東京都調布市 中部日本本部:岐阜県岐阜市)
【協力】テムジンホテルグループ
-------------------------------------------------------------------------
【参考資料】
2014年ノモンハン事件75周年 日蒙共同学術調査
【報道】
The Asahi Shimbun 2014.8.28 -Social Affairs-
Details of former Soviet positions in Mongolia unveiled
 PDF 朝日新聞 2014.7.8朝刊 社会面(39面)記事掲載
PDF 朝日新聞 2014.7.8朝刊 社会面(39面)記事掲載
朝日新聞DIGITAL 「ソ連の対日進攻拠点明らかに モンゴルに巨大陣地跡」
【シンポジウム】
研究報告活動:ノモンハン事件シンポジウム 2015年2月 東京:サピアタワー  292KB
292KB
2009年ノモンハン事件70周年日蒙中三国共同調査
【報道】
朝日新聞DIGITAL スライドショー番組「ノモンハン 70年後の戦場を訪ねて」
ノモンハン事件調査(旧満州国 西部国境地帯 内モンゴル側)過去の報道
 topページへ戻る 総目次ページへ移動する
topページへ戻る 総目次ページへ移動する


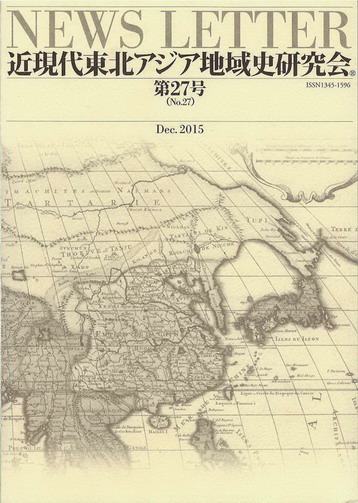
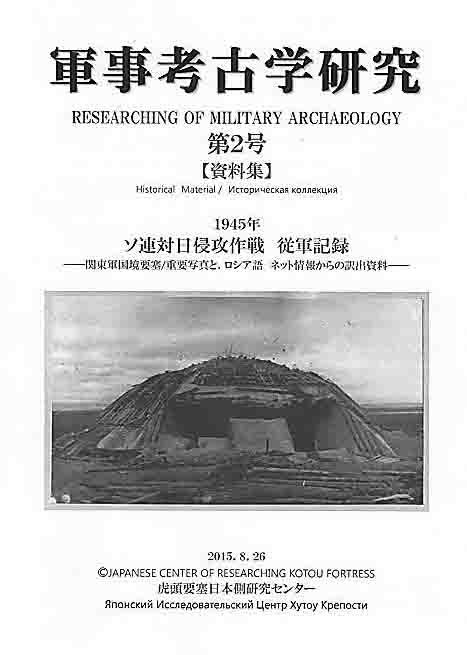






 ブーキン氏が注目した
ブーキン氏が注目した








