|
森永ヒ素ミルク中毒事件とは?
昭和30年(1955年)、西日本を中心に発生した、森永乳業の粉ミルクによる世界史上最大の乳幼児大量死亡被災事件。
森永乳業の粉ミルクを飲んだ乳児ら約1万2159人がヒ素中毒にかかり、事件発生後1年以内の間に亡くなった赤ん坊だけでも131人にのぼる。
事件史、救済運動史の詳細は、我が国ではほとんど出版されていないが、数々のライターが書いた良書が自費出版されており、資料館ホームページの文書庫で様々なテーマの文献が公開されている。だれでも無料でダウンロードできる。
森永乳業は、当時、親会社の森永製菓から製菓を支えるという目的で分社して以降、猛烈な営業活動を展開しており、原料調達を遠距離から行い、その過程で品質が劣化していた原乳を新鮮に見せかける目的で第二燐酸ソーダを添加していた。腐敗の進んだ酸化した原乳は乾燥すれば粉ミルクに見える。だがお湯に溶かす時に溶けにくいため、品質の悪さが露見する。この化学物質を「中和剤」として添加すると、溶解速度がアップするので、母親に対して品質をごまかすことができる。
だが、そうはいっても、当時他の乳業各社はこのような物質を添加することはしなかった。この時点ですでに、粉ミルク製造会社として非常識極まりない行為であるが、加えて、幾重もの非常識な行為を積み重ねた。
森永は粉ミルクに投入するにあたり、局方薬や試薬一級品の「第二燐酸ソーダ」ではなく、産業廃棄物由来の工業用燐酸ソーダを使った。工業品由来、つまり無規格品の第二燐酸ソーダは当時、脱色精製されて一見きれいな結晶体に見えるが、もちろん食品に投入するものではなく、全く別の用途、たとえば工場での洗剤や殺虫剤に使われていたしろものであった。
これをおろしていた薬品問屋は、当時の国鉄に、蒸気機関車のボイラー内部の洗浄剤として納入したが、国鉄は洗剤といえども、この工業品由来の物質を受け入れ時に検査しており、砒素の含有量が多いと、と問屋に突き返している。
つまり、産業廃棄物由来の工業用第二燐酸ソーダには成分保証がなく、砒素を含む有害な様々な不純物が混入しうるということは、あらかじめ自明の物質である。(「工業用第二燐酸ソーダ」にも、もちろん致死量のヒ素が混入していない時期もある。それは偶然性に左右される。森永はこれを逆手にとって、「使用の初期は中毒が起こらなかった」とか「規格品と同等の値段で購入していたから粗悪品とわかって入手していたわけではない」などと、あらゆる詭弁を動員して、検察の訴訟構成の不備をつき、一審は無罪を勝ち取った。差し戻し審では、「無規格品である工業品由来の第二燐酸ソーダ」を使用したことこそが、森永の最大の罪であるというシンプルな知見が採用され、森永は有罪となった。
まだある。森永は原乳が腐敗していたことをよく自覚していた。当時でも食品に投入してはいけないことになっていた、「過酸化水素水」を原乳に投入するというあり得ないことをやっていた。これはヒ素中毒の衝撃があまりに大きすぎて、陰に隠れてしまい見過ごされがちな森永の行為である。どんな原料を使用しているかを森永乳業が、もっともよく自覚していた証拠である。
「第二燐酸ソーダ」をめぐる論点で、原審から判決が逆転した経過には今日的教訓が多く、科学と法の分野からも最新の分析が加えられ、新しい知見が提出され続けている。2021年12月に出版された中島貴子氏の『科学技術のリスク評価』には、この砒素の原因物質の登場をめぐるもっとも重要な部分が、科学の素人にもわかりやすくかかれ、さらに森永の詭弁の本質と、司法が騙された背景要因が的確にまとめられている。
事件当時森永は、卸問屋から、「用途を告げずに」この工業品由来の第二燐酸ソーダを買っていた。猛毒のヒ(砒)素など不純物がいろいろと混入した、最悪の第二燐酸ソーダ「様」(もはや第二燐酸ソーダともいえない物質)のものを、赤ちゃん用粉ミルクに安定剤として添加していたのだった。
事件発覚のだいぶ前から、森永乳業は中毒通報を受けていた事実があるが、通報者に圧力を加え、遂に大量被害が発生し、その発生のさなかでも、森永は隠蔽工作に奔走していた。
森永乳業は、粉ミルクの出荷にあたっての検査も省いていた。新聞広告で「赤ちゃんのために」と「粉ミルクで丸々太った赤ん坊」を写真入りで大宣伝していた一方で、企業体質としては、もはや、人の口に入るものを作っているという自覚さえ喪失した状態であった。
そのために、乳児の大量死と終生に及ぶ重大な後遺障害が発生し、人類史上最悪・未曾有といわれるヒ素中毒事件となった。急性ヒ素中毒による赤ん坊の死者は公式発表されているものだけでも131人(事件発生後1年以内に限っての死者)、中毒患者は1万2159人に及んだ。現在、大人になるまでに死亡した被害者の総数は1200人を超えていると言われる。今なお重篤な障害に苦しむ被害者が多数おり、軽症者といえども、被害に悩み続ける心情は同じであり、また、年齢とともに被害が重症化する不安に悩まされている。
なお、奇妙なことに、一缶ごとのヒ素の含有量は異なっていた。森永乳業徳島工場では、当時計量器が故障しており、この猛毒添加物を、「目分量」で投入していたのである。「はかり」を修理する暇も惜しんで、猛毒の混入した粗悪な得体の知れない添加物を乳児の唯一の栄養源となる粉ミルクに、せっせと放り込んでいたのである。
更に重大なのは、事件が発覚したあとも14年から20年にわたって、国、医学界、メディアを囲い込んで被害者家族の訴えを社会的に「黙殺」させ、「後遺症はありえない」「赤ちゃんの症状は、原病からくるものである」「問題は何もない」「事件は存在しない」などと、社会的抹殺という手法で徹底的に弾圧し続けた森永乳業の体質である。国やメディア、弁護士にウラから手を回し、表向き「利害関係者から独立した第三者委員会」という世間受けする機関を立ち上げ、それを操って、被害者を無視した強引な「手打ち」を発表し、一方で「森永奉仕会」という組織を作って国立大学をはじめ全国の大学に研究費という名目で潤沢なカネをばら撒いた。医学界や専門家を見事に買収した。
それは街の開業医でさえ問題を指摘できないように医師を縛ることであった。ヒ素を飲まされたのち後遺症に苦しむ赤ん坊を病院から追い出すために、「診断基準」なるものを当時の小児科学会の権威(阪大小児科の権威、西沢教授と岡山大学の浜本英次教授)を筆頭にして、森永に奉仕する内容に作り変えてしまった。これは「治癒判定基準」と言われ、後遺症に苦しむ子どもを「科学の装いでもって」強引に「完全治癒したことに」してしまうというものである。子どもの命を守るべき小児科医が、被害に苦しむ子どもを圧殺する先頭にたった。
戦後、「御用学者」という言葉を生み出し、実際に大量に生み出した事件の原点ともいうべきものである。この方式は、その後の水俣病でも悪用された。ちなみに「森永奉仕会」は、その後も解体されることなく、「公益財団法人」として今も存在し続けている。
また、一方の被害者の親を買収し、「問題は何も解決されていない」と訴える被害者家族へ襲いかからせ、「被害者が金取り集団」であるかのように世間に印象づけて市民からの共感を排除するといった非道なプロパガンダの展開や、「内輪もめ」「内紛」を演出して国民と切り離し、陰に隠れて糸を引きながら、被害者を自滅させようとする巧みな手法も、この事件から開発された。金と引き換えに、こどもの健康と人権を売り渡す親。こういう親に感化されたこどもの存在も例外ではない。森永乳業は金の力で、こういう親をつくり続け、被害者家族の尊厳を丸ごと奪い続けることに、なんのためらいも持っていない企業である。
森永乳業は、カネにものを言わせた宣伝活動で、表向きの美しいイメージをつくり上げる一方、裏側から不当なコントロールを行う技術に長けており、それに一切のためらいをもたない。だから消費者はだまされる。この背景には森永乳業に知恵を貸す大手広告代理店・電通の関与があきらかとなっている。
さらに看過できない歴史的背景として、同企業が分社する前に所属していた現在の親会社である森永製菓(現・森永乳業の筆頭株主)が、創業当時から軍部に取り入って市場を拡大するやり方をとっていたことや、戦前から「練乳」などの統制物資に関与していたこと、戦時中の戦争遂行・軍国主義のプロパガンダ技術を向上させるため、当時の「報道技術研究会」を通じて電通(旧:同盟通信社-プロパガンダ実行機関-通信部門は解体されたが、広告部門が「電通」として生き延びる)が森永製菓と特別な蜜月関係を構築していたこと、そこから得られた政界とのパイプの存在が森永事件の圧殺に関係しているらしいこと。まだまだ解明すべき興味深い要素・問題は多く存在している。
資料館はその歴史的検証を通じて、「現在、進行している作為」、すなわち、「産業公害は日本では過去のこと」「現在はまったく問題はない」「被害者は今では森永企業に感謝している」かのような言説の「意図的な流布」の背景にあるものに対しても分析的アプローチを続けている。
今、一見、世間に情報が氾濫しているように見えるが、我々市民がいざ問題に直面したとき、「有名人」が撒いた言説や、ネット百科事典など安直に入手できる情報だけを参照している限り、事実や解決策となるヒントを把握できないという現実にも、また直面している。
|
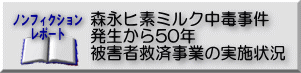

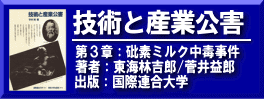
 トップページへ戻る
トップページへ戻る